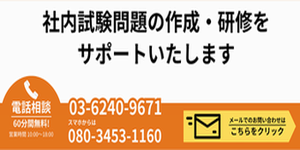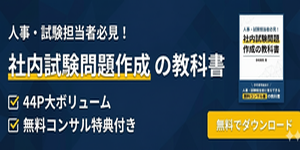次の社内研修で学ばせたい。著作権の基礎知識と許諾がなくとも使えるケース
近年、IT技術やネットワーク化の急速な発展により、誰もが他人の著作物を利用できる環境となっています。
とくに、画像や統計の引用などは気軽に行われていますが、本来、著作権は厳重に保護された権利であり、簡単に利用できるものばかりではありません。
そのため、思わず行った行為が、トラブルや賠償問題となり、会社の金銭的リスクや信用低下につながることもあります。
この記事では、通常の業務をするうえで最低限知っておきたい著作権の内容や、権利者の許諾がいる場合といらない場合、違反をした場合のペナルティについて解説いたします。
著作権とは?その法的な位置づけは?
著作権や著作物の定義・性質は、以下の通りとなります。
著作権の発生時期
著作権は、著作物が創られた時点で「自動的」に発生する権利です。
他の権利のように取得のための「申請」や「登録」などの手続きをする必要ありません。
このように、創作のときに自然に発生するルールを「無方式主義」といいます
著作権の主な内容
第17条(著作者の権利)
著作者は、「著作者人格権」並びに「著作権」を享有する。
2 著作者人格権及び著作権の享有には、いかなる方式の履行をも要しない。
著作権法には「著作権」という名称の権利は規定されていません。
しかし、一般的に著作権とは、他人が「著作物を無断で利用や公表、譲渡等すること」を止めることができる権利とされており、その内容は
▼ 著作者人格権
▼ 著作権(財産権)
の2つで構成されています。
Ⅰ 「著作者人格権」
著作者の精神的利益を守る権利です。なお、著作者に専属する権利であるため、譲渡することはできません(第59条)。
具体的には、著作者人格権は、次の4つの権利で構成されます。
| 公表権 | 公表されていない著作物について、公表するかどうか、公表する場合はいつ、どのような方法で公表するかを決定できる権利 |
| 氏名表示権 | どのように著作者名を表記するかや、ペンネーム等で表示するかを決定できる権利 |
| 同一性保持権 | 著作物を無断で勝手に改変させない権利 |
| 名誉声望保持権 | 著作者の名誉や声望を害する方法による著作物の利用を禁止できる権利 |
Ⅱ 「著作権(財産権)」
著作者の財産的利益を守る権利です。
財産権の一種であるため、譲渡や相続することが可能です。(第61条)。
著作権の保護を受ける著作物とは?(著作物の定義)
著作権は知的財産権の一種であり、著作者等の権利保護を図るための法律です。
しかし、著作物のすべてが著作権による保護を受けるわけではなく、
「著作物の定義を満たすもの」+「法的保護を受ける要件」
という2つの条件を満たす必要があります。
著作物は、著作権法により、次のように定義されています。
第2条1号(定義)
一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう
つまり著作物とは、以下の4つの要件を満たすものとなります。
| ① 「思想又は感情」を対象としたものである ② 「創作的」なものを対象としたものである ③ 何らかの形で「表現したもの」である ④ 「文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属する もの」である |
ただし、以下の点に注意が必要です。
①には、単なる事実やデータは対象とはならない
②には、誰が表現しても同じになるものや模造品は含まれない
③には、頭の中にあるアイデアなどは対象とならない
④には、工業品は含まれない
では、これらのうちどのようなものが著作権法による保護を受けるのかについては、著作権法第6条で次のように規定されています。
著作権法により保護を受ける著作物
| 一 日本国民の著作物(国内法人及び国内に主 たる事務所を有する法人を含む。) 二 最初に国内において発行された著作物(最 初に国外において発行されたが、その発行 の日から30日以内に国内において発行され たものを含む。) 三 前二号に掲げるもののほか、条約によりわ が国が保護の義務を負う著作物 |
著作権以外の権利
著作権は知的財産権の一部の権利であり、その他の権利には次のようなものがあります。
🔳著作隣接権
著作隣接権とは、著作物の創作者ではないものの、著作物の普及に貢献した者に対して契約にもとづかずに与えられる法律上の利益で、実演家、レコード製作者などにに認められる権利です。
複製権、上演権、頒布権、譲渡権、貸与権、二次的著作物の利用に関する権利などがあります。
🔳特許権
特許権とは、特許を受けた「発明」(自然法則を利用した技術的思想の創作のうち、高度のもの)を一定期間独占的に実施することができる財産権の一種です。
権利の侵害があったときには、この権利にもとづき排除することができます。
🔳実用新案権
実用新案権は、物品の形状、構造または組み合わせに係る考案を保護するための権利です。
考案とは、自然法則を利用した技術的思想の創作をいい、発明と違い高度であることを要しません。
🔳意匠権
意匠権は、ものや建築物、画像のデザインに対して与えられる独占排他権です。
主に、工業上のデザインが対象となります。
🔳商標権
商標権とは、商品又はサービスについて使用する商標(マーク)に対して与えられる独占排他権で、文字、図形、記号の他、立体的形状や音等も保護の対象となります。
🔳営業秘密
営業秘密とは、不正競争防止法が定める企業が営業活動や研究・開発から生み出した重要な秘密の情報のことをいいます。
これを侵害した場合には、刑事罰や民事上の損害賠償請求、差止請求の対象となります。
それぞれの権利の保護期間
著作権他の権利は、それぞれ以下の期間保護されます。
| 権利の種類 | 権利の保護期間 |
| 著作権 | 創作の時から著作者の死後70年 |
| 著作隣接権 | 実演等を行った時から70年 |
| 特許権 | 出願から20年 |
| 実用新案権 | 出願から10年 |
| 意匠権 | 出願から25年 |
| 商標権 | 登録から10年、更新あり |
| 営業秘密等 | 定めなし |
著作権を侵害した場合のペナルティ
他人の著作権を侵害した場合は、次のようなペナルティを受ける可能性があります。
● 刑事関連
【個人による侵害】
最大10年以下の懲役 又は 1,000万円以下の罰金、あるいはその併科 (第119条第1項)
【法人による侵害】 3億円以下の罰金
※いずれも原則、親告罪(被害者の告訴が必要となる罪) ただし、海賊版DVDの販売等を除く
● 民事関連
① 差止請求(第112条)
著作権の侵害をされた者は、侵害者の故意又は過失を問わず、「侵害行為の停止」を求めることができます。
また、侵害のおそれがある場合には、「予防措置」を求めることができます(第112条、第116条)
② 損害賠償請求(民法第709条)
故意又は過失によって他人の権利を侵害した者に対して、その損害を賠償するよう請求することができます。
③ 不当利得返還請求(民法第703条、第704条)
その行為が違法であることを知らなかった場合は「その利益が残っている範囲での額」を、知っていた場合には「得た利益に利息をつけた額」を、それぞれ請求することができます。
④ 名誉回復等措置請求(第115条、第116条)
侵害者に対して、著作者等として「名誉・声望を回復するための措置」を請求することができます。
適法に著作権を利用する方法
著作権のあるものや写真などを利用する際には、以下の方法でその許諾や権利を得る必要があります。
著作権者の許諾を得る
他人の著作物を適法に利用するための手段として、「著作者の許諾を得る」方法があります。
しかし、雑誌等の場合、個々の写真やイラスト等に関しては、カメラマンやイラストレーター自身が権利を有している場合があり、このような場合には権利者を特定する必要があります。
また、相続によりその遺族が権利を共有している場合もありますが、このような場合にも権利者を特定し、相続人の許諾を得る必要があります。
著作権の譲渡を受ける
著作者人格権の4つの権利は譲渡することができませんが、「著作権(財産権)」は、契約により権利者から譲り受けることが可能です。
譲渡の契約をする際に、二次的な利用に関する権利を含めた著作権の譲渡を受ける場合は、契約書に
「すべての著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む)を譲渡する」
と記載しておく必要があります。
なお、著作物を自由に使わせる必要がある場合に、 著作者人格権を行使しない旨を規定するケースもありますが、これについては無効とする考えもあるため注意が必要です。
文化庁長官の裁定を受ける
著作権者等の許諾を得ようとしても、
「だれが権利者なのかわからない」
「権利者がどこにいるのか分からない」
という場合もあります。
このような場合は、権利者本人から許諾を得る代わりに「文化庁長官の裁定」を受け、相当の「補償金」(使用料)を供託することで、著作物を適法に利用することができます。
ただし、許可を得るためには、あらかじめ権利者を探したり、その方と連絡を取るための「相当な努力」をすることが条件となります。
許諾を得ずに著作権を利用できるケース
著作物を利用するには、原則、権利者の許諾を取るなどの手続きが必要となりますが、以下の場合は許諾なしで利用することができます。
許諾を得ずに利用できる例
● 私的使用のための複製(第30条)
家庭内など限られた範囲内で、仕事の目的以外で、使用する本人が複製する場合
ただし、コピーガードの解除などは禁止されます。
● 付随対象著作物の利用(第30条の2)
写真撮影、録⾳・録画などを⾏う際、主体となる対象以外の著作物が小さく「写り込む」場合
● 図書館等での複製(第31条)
● 引用・行政の広報資料等の転載(第32条)
● 学校その他の教育機関における複製等(第35条第1項・第2項)
許諾を得ずに利用する場合の注意点
以上の方法で他人の著作物を許諾を得ずに利用する場合でも、次の点に注意する必要があります。
● 目的外の利用
許諾不要でコピーを作成する場合でも、そのコピーを本来の目的外で使用することはできません。
● 出典の明示等
許諾不要で他人の著作物を利用する際には、「出所の明示」や「補償金の支払い」をすべき場合が定められていることがあります。
● 著作隣接権の利用
許諾不要で他人の著作物を利用できる場合には、その付属する権利である「著作隣接権」も利用することができます。
効果的な著作権研修のためのポイントとプログラムの例
著作権研修では、基本的なルールを学ぶ他、実際の仕事の状況を踏まえた解説や事例を交えたルールの説明など、具体的な状況を取り入れた研修とすることで、より深く理解することができます。
仕事の現場で起きやすい違反
たとえば、「ネットで見つけたフリー素材の写真を自社のチラシに使う」、「新聞の記事を会議の資料として配布する」などは、よくしてしまいがちな行為ですが、いずれも違反となる可能性があります。
フリー素材については、私的利用はOKでも商用利用が禁止されている場合もあり、また、新聞記事の無許可のコピーや配布は原則、著作権違反となります。
このように社内で行われている身近な例を切り口としたり、振り返ることで、より実務に沿った研修とすることができます。
著作権侵害の事例
最近では、企業による著作権違反がクローズアップされ、新聞や雑誌に報道される事例や、本人から使用の差止め・損害賠償を請求されるケースが増えています。
そのため、研修では近年の違反の傾向やその違反により具体的にどのような損害が生じたのかをケーススタディとして学ぶなどが考えられます。
具体的な研修プログラムの例
著作権研修における具体的なプログラムとしては、以下のようなものがあります。
(1)著作権法の基礎(著作権の目的、定義等)
(2)著作権者と著作物
(3)著作権の内容と著作隣接権
(4)著作権以外の知的財産権
(5)著作物の利用と保護期間
(6)著作権者の許諾が必要ない場合
(7)身近な著作権違反
(8)著作権違反とならないための対策
(9)著作権などの侵害行為
(10)著作権違反の事例
(11)ワークスタディ(違反となるかどうかの
回答や、対策の発表)
なお、最近では「取適法」や「女性活躍推進法」の改正も行われているため、これらについてもあわせて参考にしてください。
まとめ
著作権は業務で触れることの多い権利ですが、その分気がつかないところで違反や他人の権利の侵害をしてしまいやすい権利といえます。
著作権違反によるトラブルを引き起こさないためには、研修等で正しい知識を得ておくのは必須ですが、社内の事例を積極的に取り上げ、情報を共有する、検討するなどをするとさらに深い理解につながります。
| テストビジネスでは、社内試験問題の作成・実施に関するご相談を承っております。 また、ご希望の方には、正式なご依頼前に無料で見本問題を作成・ご提出するサービスもございますので、お気軽にお問合せください。 |