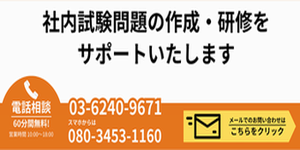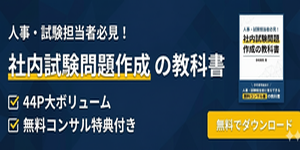社内研修の3つのスタイルと実践プログラムの具体例

社内研修にはいくつかのスタイルがあり、どれを使うかで伝わり方や受講者の理解度が大きく変わります。
また、スタイルだけでなく、これを組み合わせてどのようなプログラムで行うかによっても、学習効果に違いを生じます。
そのため、研修をする際には、参加者の属性、目標などにあわせてこれらを適切に選択することで、より高い成果を得ることができます。
この記事では、代表的な3つの研修スタイルと組み合わせプログラム、これまでの研修との違いについて解説いたします。
社内研修をする意味
社内研修はなぜ行うのでしょうか。
また、それにより何を得られるのでしょうか。社内研修を行うことには、次の3つの意味があります。
会社の理念や知識を効率よく得るため
企業には、社員に必ず知っておいてほしい「理念」や「ミッション」、「業務をするうえで欠かせない知識」があります。
しかし、これらをマンツーマンで個別に伝えたり、教育するのは、不経済、時間のロスであり現実的ではありません。
けれど、対象者を一度に集めれば、経済的なだけでなく、必要に応じて何度も行うことができます。
集合型・オンライン型を問わず、社内研修ではこのように「短時間で」、「必要なことを」、「多くの人に伝える」ことができるため、効率的に人材の育成をすることができます。
経験を共有するため
どのような内容の研修でも、一人に対して行ったのでは、その個人の能力以上のパフォーマンスを発揮することはできません。
けれど、同じ目的を持った人間が集まり、研修を行えばお互いに刺激となるだけでなく、その体験は共有され、大きな気づきを得るきっかけにもつながります。
また、複数人が参加することで、さらに、多様なグループワークを行うことも可能となります。
仲間やチームワークを得るため
研修でグループワークなどの共同作業をすることで、それまで知らなかった方と知り合いになるきっかけを得たり、チームワークを育てることができます。
また、講義の空き時間や自由時間、研修後の交流を通じ、情報交換を行うことで人的ネットワークを強化することができます。
3つの学習法と研修のスタイル
研修には、「どういう形式で行うか」の学習法と、「どのような進め方をするのか?」というスタイルが、それぞれ3つずつあります。
学習法
OJT(On-The-Job Training)
OJTは、上司が職場の業務を通じて部下を指導・育成していく教育方法を意味し、従来の職場で伝統的に行われてきた方法です。
OJTによる学習には、次のような特徴があります。
- 特別なコストがかからず、実務に即した実践的な教育ができる
- マンツーマンにより、相手の習熟度にあわせられる
- 業務優先の指導となってしまう
- 知識の伝達(上司側)や理解度(部下側)にムラがでやすい
Off-JT(Off-The-Job Training)
Off-JTは、現場から離れて指導・教育をしていく方法を意味し、外部講師を招いて行う研修などが代表的なものとなります。
Off-JTによる学習には、次のような特徴があります。
- 職場を離れた開放的な環境で教育ができる
- 専門家による正しい知識を得ることができる
- コストや特別な時間がかかる
- 実務と離れた内容となりやすい
自己啓発
自己啓発は、企業に頼らずに、個人自らが学習し、知識を習得する方法であり、資格試験の取得などに向いた方法といえます。
自己啓発による学習には、次のような特徴があります。
- 主体的に自分のペースで学習できる
- 個人が学習費用を負担しなければならない
- 内容が自分の興味に偏ったものとなりやすい
- 知識の正確な評価がしにくい
なお、試験や研修を効果的に行うためには、よくある失敗パターンや実践的に行うための4つのステップを理解しておく必要があります。これらの内容については以下の記事をご参考ください。
研修のスタイル
講義型
講義型は、いわゆる「座学」といわれるタイプで、参加者が一つの教室に集まり、テキストを中心に学習するスタイルです。
1回の講義で効率的に必要な知識を多くの人間に伝達できるメリットがあるため、未経験者や初心者などに対しても効果的です。
しかし、その反面、すでにその内容を経験している方やある程度の知識や経験のある方にとっては物足りないものとなり、また、受け身の参加となるため、自分の知識や経験を発揮しにくいといった特徴があります。
ワークショップ型(問題解決型)
ワークショップ型はいわゆる「問題解決型」といわれる学習スタイルです。
普段の業務や生活の中で、関係のある問題に対し、自らの体験と考察を繰り返しながら、問題解決をして行きます。
参加者主体の方法であり、成人やすでに何らかの学習をしている方に向いています
しかし、その半面、比較的、少人数を対象とするため効率の点で劣り、成果が指導する人間の力量に左右されるといった問題があります。
省察型
省察型とは、ワークショップ型をさらに発展させたものです。
ワークショップ型は、あらかじめ必要なテーマや材料、スキルが用意されており、これらを使って問題解決をしていく手法です。
これに対し、省察型ではこれらは用意されておらず、ワークの中で参加者自らが課題を見つけていく点に違いがあります。
たとえば、ワークの中で自分の考えや行動を振り返り、自律的に見つめなおすなどがこれにあたります。
個々の参加者にあった深い省察や学習が可能となり、参加者同士の相互作用が活かしやすくなります。
その半面、時間がかかり効率が悪い、学習をする人によって差が出やすいなどの特徴があります。
具体的な研修の実践方法
研修は大まかには「前半部」、「後半部」、「まとめ」の3つのパートに分けられます。
ここではそれぞれの進め方の注意点とパートごとの研修スタイル・組み合わせをご紹介いたします。
研修のパートごとの進め方と注意点
導入部
研修の導入部は、「あいさつ」・「講師の自己紹介」・「簡単な講義の進め方や注意事項」が中心となります。
当日はある程度早めに教室に入っておき、席の配置、室温、通風、日差し、スライドの準備や動作の確認、配布資料、マイクの調整、研修担当者との最終的な連絡など、講義の下準備をしておきます。
なお、研修では「見にくい」よりも「聞きにくい」の方が、より大きなストレスとなります。
そのため、音声(全員に届いているか、音割れやハウリングがないか)についてはとくに注意する必要があります。
また、時間に余裕がある場合には、先に入ってきた参加者と雑談などをすることで、多くの情報を引き出すことができるだけでなく、緊張せずに始められるなどの効果が期待できます。
前半部
研修の前半部では、テキストやスライドを使用した、座学タイプの講義が中心となります。
最近では、パワーポイントのみで講義をする方が増えていますが、その場合にはスライドの枚数が多量となる、講義がせわしなくなりやすい、資料の内容が簡単なものとなるといった特徴があります。
逆に、テキストだけでの講義では、集中力が続かなかったり、全体的にメリハリのない内容となりやすくなります。
したがって、講義では基本的な内容はテキストに記載しておき、その要点だけをスライドにするという方法にすると、参加者の集中力を切らさず、メリハリをもって進めることができます。
研修で重要なのは「面白い」ではなく、「わかりやすい」や「共感できる」といった体験です。
したがって、ジョークをところどころに挟むのは構いませんが、できるだけ最小限にしないと参加者の興味がそちらにそれてしまい、肝心の内容が記憶に残りにくくなってしまうことに注意してください。
後半部
研修の後半部では、「講義のみ」または「講義+ワーク」を行います。
しかし、時間に余裕がない場合やワークに力を入れたい場合には「ワークのみ」でもよいでしょう。
なお、問題解決型や省察型のワークでは、ルール説明や動き出しまでの時間、指導のための時間を見込んでおく必要があります。
また、提示した問題を回答させるタイプのワークでは、座学の延長線となったり、内容に新鮮味がなくなりやすいという傾向があります。
そのため
▼ グループごとに結果を競争させる
▼ 問題に関する体験談や失敗談を盛り込む
▼ 隣の人と意見交換をさせる
などの工夫をすると最後まで退屈せず、興味をひきやすい研修とすることが可能です。
まとめ部分
まとめは、それまでの研修の内容と、その研修で何を得られたかを振り返る場となります。
ここでは、それまでの資料ではなく、別途、ポイントがまとめられたものを用意すると見返しの必要がなく、スムーズに進めることができます。
気をつけたいのが、まとめではそれまでの講義のポイントを話すだけでなく、その研修で何を得られたかを確認することです。
研修に求めるものは、基本的な知識を得たいと考えているや、その知識を業務に生かしたい人などさまざまです。
そのため、自分が求める目標を達成できたのかを確認する場として、振り返りの時間が重要となります。
講義の内容と本人が希望する目標に開きがあっては、講義そのものが有効ではなかったということになってしまいます。
したがって、講義前のアンケートで、以下のことを確認しておくと参加者とのずれを少なくすることができます。
- その研修で知りたいことは何か?
- 研修を受けてどうなりたいか?
- どのような形式の研修を望むか?
従来の研修と工夫を加えた研修
従来の研修にある程度の工夫を加えることで、内容をさらに充実させることができます。
下図は、同じ「座学+討議」をメインとした研修を比較したものの一例です。
左がテキストの内容の解説や討議をするだけなのに対し、右では事前アンケートで目標や期待するものを確認したうえで、それをグループ討議のテーマや振り返りに活用します。
| これまでの研修 | 工夫を加えた研修 |
| ● 必要な基礎知識についての座学 ↓ ● 与えられた課題に関するグループ討議 ↓ ● 知識の確認テスト | ● 学びたいことについての事前アンケート ↓ ● 必要な基礎知識についての座学 ↓ ● 社内の課題等をテーマとしたグループ討議 ※現状の再確認と対策の考察をメイン ↓ ● 個人ごとの振り返りと行動目標の発表 |
このようにはじめに目標や成果を決めてそれを参加者と共有することで、参加者とのブレを少なくできるだけでなく、振り返りでも本人の納得した結果を得やすいものとなります。
代表的な研修プログラムのパターン
研修プログラムには主に3つのパターンがあります。
それぞれ一長一短があるため、研修の目的にあわせて取り入れるようにしましょう。
<講義→ワーク→振り返り>
最も多く行われている研修のパターンです。
最初に講義を行うことにより、あらかじめ必要な知識をインプットできるため、次のワーク等の準備となるだけでなく、ワークで何をするのかという要点が理解しやすくなります。
▼ 注意点
講義が強く印象に残っている場合、その後のワークもそれに沿った進行や結果となってしまいやすくなります。
また、講義とワークに時間を取られてしまうと、振り返りが不十分になる恐れがあります。
例)
・新入社員研修
・管理職研修
・実務の入門研修
<ワーク→振り返り→講義>
はじめにワークで考えたり行動してもらうことで、気づきを誘発し、それを振り返った後に講義で知識を整理するというパターンです。
難解なテーマや普段取り扱わないような内容を扱うときに効果的であり、考えを具体から一般へと拡散させることで理解を深める狙いがあります。
また、はじめにワークと振り返りという共有体験をするため、参加者同士の共感度や交流度を高めることができます。
▼ 注意点
ワークに慣れていない人が多いと、スムーズに進まず、予定した効果が得にくいものとなります。
また、参加者を混乱させないために、シッカリした流れや目的に関する説明、シナリオなどが必要となります。
例)
・防犯防災研修
・リスクマネジメント研修
・新たな業務の研修
<振り返り→講義→ワーク>
自分の今までの経験を振り返り、そこでの気づきを研修の出発点にするパターンです。
振り返りをはじめに行うことで、その後の講義が理解しやすくなる、ワークに意欲的になります。
そのため、課題の解決をしたい人には気づきを与え、目的に沿った研修となりやすいという特徴があります。
▼ 注意点
それまでの参加者の個々の経験の違いが成果の差となりやすく、各パートを違和感なくつなげるための工夫が必要となります。
例)
・モチベーション研修
・キャリア形成研修
・ハラスメント研修
以下の記事では、社内研修計画の作り方の手順とポイントついて解説していますので、あわせてお読みください。
まとめ
以上のように、研修はいくつかの型やスタイルがあり、これらを組み合わせて行うことで、単独のものより高い効果を得ることができます。
これからの研修には、単なる知識の詰め込みだけではなく、学んだことを活かして組織の共通のビジョンを作ったり、個人の課題を解決するためのツールとしての役割が期待されています。
そのためには、これまで通りのやり方に固執するのではなく、研修の目標や参加者の希望にあわせた柔軟な設計が求められます。
| テストビジネスでは、社内試験問題の作成・実施に関するご相談を承っております。 また、ご希望の方には、正式なご依頼前に無料で見本問題を作成・ご提出するサービスもございますので、お気軽にお問合せください。 |