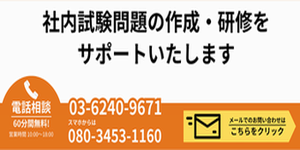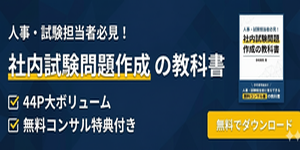すべての企業が押さえておきたい。労務管理に必要な法律と研修方法

労務管理は、すべての企業において欠かせない重要な業務の一つです。
労務管理は人の労働を管理するものですが、労働基準法をはじめ対象となる法令の範囲が広いため、全体を把握しにくいと感じている方も少なくないと思います。
しかし、労務管理を怠ると社員の労働状況が把握できず、不満やモチベーションの低下を招いたり、最悪、死傷事故にもつながりかねません。
この記事では、労務管理の役割と担当者が最低限理解しておくべき法律、労務研修のポイントについて解説いたします。
労務管理の目的
労務管理とは、従業員の勤怠状況や賃金、労働時間の管理、安全衛生など、労働条件全般に関する事項の管理をすることです。
「人」に関連する業務が中心であり、労務管理の優劣は、従業員の生活や肉体的・精神的モチベーションに大きく影響します。
労務管理の目的
労務管理の目的は、従業員の労働に関する環境を把握・調整して、人の生産性を向上することです。
労務管理では、労働者の安全・労働時間・賃金の管理が最も重要となりますが、最近では、パワハラ・セクハラ対応などの精神面へのサポートやケアの比重も大きくなっています。
労務担当者とは?
企業には総務、人事など人の管理に関する部署はいくつかあります。
しかし、一般的には、よほど大きな企業でない限りこれを専門で担当する部署はなく、たいていは総務部か人事部が行っています。
また、労務担当は、衛生管理者や安全管理者のように配置が義務付けられているわけではありませんが、労務に関する業務は会社の規模にかかわらず必須のものとなります。
労務管理の業務
労務管理においては、以下の3つが重要な業務となります。
各種名簿の作成
従業員の属性、賃金、勤怠を管理するため、その目的にあわせた名簿を作成することが義務付けられています。
労働者名簿
労働者名簿とは、労働基準法第107条により作成が義務づけられた、従業員の氏名や住所、雇用年月日などの情報を記載した書類です。
この規定に違反した場合には、30万円以下の罰金が科されます。
賃金台帳
賃金台帳とは、労働基準法第108条により作成が義務づけられた、各従業員の賃金や支払い状況等をまとめた書類です。
この規定に違反した場合には、30万円以下の罰金が科されます。
出勤簿
出勤簿は、労働基準法第108条により作成が義務付けられた、従業員の労働時間や出勤日数を把握するための帳簿です。
この規定に違反した場合には、30万円以下の罰金が科されます。
社会保険や雇用保険の加入手続き
社員の入社や退社の際には、「健康保険」や「厚生年金」、「雇用保険」、「労災保険」への加入手続きが必要となります。
また、届出事項に変更があった場合には、法定の期間内に所轄の役所へ変更届を提出しなければなりません。
給与計算
給与計算は、企業が従業員に対して支払う給与・賞与額を算定するために行う業務です。
具体的には、総支給額から税金などの各種控除や手当を調整し、最終的に支払う給与額を計算します。
その他の手続き
労務管理においては、その他の手続きとして、「労働条件通知書」の作成・管理の他、労務に関する規定の作成・変更などの業務を行います。
また、最近ではメンタルの管理や相談を行うところも増えています。
労務管理者が抑えておくべき労働関係法
労務管理者が正確に業務を行うには、民法の雇用や労働安全衛生法、最低賃金法、労働契約法などの労務に関する法令を理解している必要があります。
ここでは、労務担当者が押さえておくべき法令とその概要をまとめました。
労務に関する法律
労務担当者が押さえておくべき代表的な法律としては、以下のものがあります。
| 法 令 | 概 要 | 重要項目 |
| 民法 | 雇用契約の基本事項について民法623~631条(雇用)で規定 | 内容は労働基準法や労働契約法により修正される |
| 労働安全衛生法 | 労働者の健康や安全を守るために制定 | 健康診断の実施、作業主任者の選任、雇い入れ時の教育他 |
| 最低賃金法 | 国が定める最低賃金額以上の賃金の支払い義務を規定 | 最低賃金未満の賃金の支払いは無効。差額の支払い義務 |
| 労働契約法 | 労使間のトラブルを防止するための契約ルールを規定 | 労働契約の5原則。基準に達しない労働契約の無効 |
| 労働基準法 | 使用者が最低限満たすべき労働条件を規定 | 賃金支払い、労働時間、休日・休憩、労働契約の禁止事項他 |
民法
民法はすべての契約のもととなるルールを規定しており、企業と労働者間の関係については債権編の「雇用」、「不法行為」、「損害賠償」、「使用者責任」、「公序良俗」等の部分が該当します。
しかし、民法はあくまで当事者間の関係を定める私法であるため、一部の規定を除き、以下のような特徴があります。
▼ 内容を合意により変更することができる
▼ 適用を強制する力はない
▼ 同じ内容については、特別法が優先する
そのため、民法では基本的な規定がどのようになっているのかを確認したうえで、それらの規定が特別法によりどのように修正されているのかを理解することが重要となります。
なお、民法については「次の社内研修で学ばせたい。民法の要点と研修で教えるポイント」の記事で詳しくまとめています。
労働安全衛生法
労働安全衛生法は、労働者の健康や安全を守るために制定された法律です。
この法律は、労働災害の防止や職場環境の改善を目的としており、事業者に対して労働者が安全で快適に働ける環境を整備する義務を課しています。
労働基準法と同じく、労働者の保護に関する法律ですが、労働者の権利よりも健康と安全に重点を置いている点が労働基準法と異なります。
【 重要な規定 】
● 健康診断の実施(労働安衛第66条)
事業者は、労働者に対し、医師による健康診断を行わなければならない。
● 作業主任者の選任(労働安衛第14条)
事業者は、高圧室内作業等の一定の作業については、作業主任者を選任しなければならない。
● 雇入れ時教育(労働安衛第59条1項)
事業者は、労働者を雇い入れたときは、その業務に関する安全・衛生教育を行わなければならない。
● 危険又は有害な業務安全衛生教育(労働安衛第59条3項)
事業者は、特定の危険・有害業務に労働者をつかせるときは、その業務に関する安全・衛生の特別教育を行わなければならない。
● 総括安全衛生管理者の選任(労働安衛第10条1項)
事業者は、一定規模以上の事業場ごとに、総括安全衛生管理者を選任しなければならない。
● 安全管理者の選任(労働安衛第11条)
事業者は、一定の業種・規模の事業場ごとに、安全管理者を選任しなければならない。
● 衛生管理者の選任(労働安衛第12条)
事業者は、一定規模の事業場ごとに、衛生管理者を選任しなければならない。
● 産業医の選任(労働安衛第13条)
事業者は、一定規模の事業場ごとに、産業医を選任しなければならない。
最低賃金法
最低賃金法は、使用者が支払わなければならない最低賃金額を定めた法律です。
もし、最低賃金額よりも低額の賃金を労使が合意の上で定めても最低賃金額と同額の定めをしたものとされ、事業者は最低賃金額との差額を支払わなくてはなりません。
【 重要な規定 】
● 最低賃金の支払い(最低賃金法第4条1項)
使用者は、労働者に対し、最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない。
● 最低賃金の効力(最低賃金法第4条2項)
労働契約で最低賃金に達しない賃金を定めた場合は、その部分は無効とし、その無効となった部分は、最低賃金と同じ定めをしたものとみなす。
● 罰則(最低賃金法第40条)
最低賃金支払いの規定に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。
労働契約法
労働契約法は、2008年3月に施行された、個別労働関係紛争を未然に防止するために制定された法律です。
労働契約の基本的なルールを定めることで、労働者の保護と個別の労働関係の安定化を目的としています。
ただし、他の法律と異なり、これは私法の一つとなるため、違反をしても罰則の適用はありません。
【 重要な規定 】
● 労働契約の原則(労契法第3条1項)
労使対等の原則、均衡考慮の原則、仕事と生活の調和への配慮の原則、労働契約遵守・信義誠実の原則、権利濫用禁止の原則
● 労働者の安全配慮義務(労契法第5条)
使用者は、労働者がその生命、身体等の安全を確保できるよう必要な配慮をする。
● 就業規則による労働契約の内容の変更(労契法第9条)
使用者は、労働者の合意なく、就業規則を変更して、労働者の不利益に労働条件を変更することはできない。※例外規定あり
● 就業規則違反の労働契約(労契法第12条)
就業規則の基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については、無効とする。この場合において、無効となった部分は、就業規則で定める基準による。
● 法令及び労働協約と就業規則との関係(労契法第13条)
就業規則が法令又は労働協約に反する場合には、当該反する部分については、第7条、第10条及び前条の規定は、当該法令又は労働協約の適用を受ける労働者との間の労働契約については、適用しない。
● 契約期間中の解雇等(労契法第17条)
使用者は、有期労働契約について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまで労働者を解雇することができない。
労働基準法
労働基準法は、労働者に適用される労働条件の最低ラインを定めた法律であり、労働契約に関する最も中心的な法律です。
使用者はこの基準を遵守しない場合には、罰則や行政監督の対象となります。
【 重要な規定 】
● 均等待遇の原則(労基法第3条)
労働者の国籍、信条、社会的身分により、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。
● 男女同一賃金の原則(労基法第4条)
労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。
● 賃金の定義(労基法第11条)
賃金とは、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。
● この法律違反の契約(労基法第13条)
この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となった部分は、この法律で定める基準による。
● 契約期間の原則(労基法第14条1項)
労働契約は、原則として、3年(一部のものは5年)を超える期間について締結してはならない。※例外規定あり
● 労働条件の明示(労基法第15条1項)
労働契約の締結の際には、賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。
● 解雇制限(労基法第19条)
使用者は、労働者が業務上の負傷・疾病による休業期間及びその後30日間、産前産後の女性の休業期間及びその後30日間は、解雇してはならない。※例外規定あり
● 解雇予告(労基法第20条1項)
使用者は、労働者を解雇する場合は、30日前に予告をするか、平均賃金30日分の解雇予告手当を支払わなければならない。※例外規定あり
● 賃金支払いの5原則(労基法第24条)
通貨払い、直接払い、全額払い、毎月1回以上、一定期日払いの原則
● 休業手当(労基法第26条)
使用者の責任による休業の場合は、休業期間中労働者に平均賃金の100の60以上の休業手当を支払わなければならない。
● 労働時間・変形労働時間(労基法第32条)
休憩時間を除き、一週間について40時間を超えて、1日については8時間を超えて労働させてはならない。
● 休憩(労基法第34条)
労働時間が6時間を超える場合は45分、8時間を超える場合は1時間の休憩時間を与えなければならない。
● 時間外及び休日の労働(労基法第36条)
会社に過半数組合がある場合はその組合、ない場合には労働者の過半数代表者との書面による協定をし、行政官庁に届け出た場合は、労働時間の延長し、又は休日労働させることができる。
● 割増賃金(労基法第37条)
労働時間の延長、休日労働をさせた場合は、通常賃金の2割5分以上5割以下の範囲内で割増賃金を支払わなければならない。ただし、延長労働時間が1箇月で60時間を超えた場合は、超えた時間については、5割以上の割増賃金を支払わなければならない。
● 年次有給休暇(労基法第39条)
使用者は、雇入れの日から6箇月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対しては、10日の有給休暇を与えなければならない。
● 産前産後(労基法第65条)
1. 6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産予定の女性が休業を請求した場合は、その者を就業させてはならない。
2. 産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。
● 休業補償(労基法第76条)
労働者が業務上の負傷、疾病による療養期間については、平均賃金の100分の60の休業補償を支払わなければならない。
● 就業規則の作成及び届出の義務(労基法第89条)
常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。
● 罰金の種類・両罰規定(労基法第117~121条)
・1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金
・1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
・6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金
・30万円以下の罰金
この法律の違反行為をした者が、事業主のために行為した代理人、使用人その他の従業者である場合は、事業主に対しても各罰金刑を科する。
ハラスメント
ハラスメントとは、広義には「人権侵害」を意味し、相手に不快感や不利益を与え、被害者の就業環境を悪化させる行為全般を意味します。
身体的な攻撃だけでなく暴言や無視、いじめなどの精神的な攻撃もハラスメントにあたります。
ハラスメントに関する主な法律には、以下のようなものがあります。
〇 労働施策総合推進法(主にパワハラを規定、カスハラについても追加予定)
〇 男女雇用機会均等法(主にセクハラを規定)
〇 育児・介護休業法(主にマタハラを規定)
いずれについても各法律で対応が義務となっており、これに違反した場合には勧告や企業名の公表などの対象となります。、
なお、会社内で最も多いパワハラについては「ブラック企業といわれないためのパワハラ対策とは?」の記事で詳しくまとめています。
コンプライアンス
コンプライアンスとは、一般的に「法令順守」を意味します。
これは特定の法律を指すものではありませんが、最近では、企業の考え方や意識を図るうえで、社会的にも重要な規範となっています。
コンプライアンスは「法令」だけを意味するのではなく、社会規範や企業の就業規則、労働契約など、企業が経営をするうえで守るべき規範のすべてを含みます。
しかし、コンプライアンスは企業ごとに目標とするものや内容が異なるため、研修を行う際には、
「その企業にとって、守るべきコンプライアンスとは何か?」
を明確に定義しておく必要があります。
なお、コンプライアンスについては「なぜ、コンプライアンス研修が必要?するとどう変わる?」の記事で詳しく解説しています。
各種保険と年金制度
労働者への労災保険や雇用保険等の適用など、勤務中のけがや解雇された場合の補償の対応なども労務の重要な業務となります。
雇用保険
雇用保険は、労働者が失業した場合に、生活の安定と就職の促進のための失業等給付を行う制度であり、雇用保険制度への加入は事業主の義務となっています。
雇用保険は、事業所の規模にかかわらず、以下の要件のいずれかに該当する場合には強制加入となります。
①31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること。
※具体的には、次のいずれかに該当する場合
・期間の定めがなく雇用される場合
・雇用期間が31日以上である場合
・雇用契約に更新規定があり、31日未満での
雇止めの明示がない場合
・雇用契約に更新規定はないが同様の雇用契約
により雇用された労働者が31日以上雇用さ
れた実績がある場合
②1週間の所定労働時間が 20 時間以上であること。
ただし、法人の代表取締役や個人事業主、公務員や同居親族、昼間学生は雇用保険の対象外となります。
なお、新たに被保険者となる人が入社したときには、「雇用保険被保険者資格取得届」を管轄のハローワーク)に、被保険者となった日の属する月の翌月 10 日までに提出する必要があります。
労災保険
労災保険は、労働者が業務中に生じた怪我、病気、障害、死亡と通勤の途中の事故等(通勤災害)の給付を補償する制度です。
原則として、一人でも労働者を使用する事業は、業種の規模の如何を問わず、すべてに適用されます。
また、アルバイトやパートタイマーを含むすべての労働者が適用対象となります。
ただし、法人の代表権・業務執行権を有する役員や事業主と同居している親族は、雇用保険の対象外となります。(例外あり)
労災保険は、保険関係成立届を保険関係の成立の翌日から10日以内に、所轄の労働基準監督署へ提出する必要があります。
健康保険
健康保険は、労働者やその家族が病気・怪我・出産・死亡等のときに、必要な医療給付や手当金の支給をすることを目的とした制度です。
健康保険の適用事業所には、法律によって加入が義務づけられている強制適用事業所と、任意で加入する任意適用事業所の2種類があります。
次の①か②に該当する事業所は、強制加入となります。
①次の事業を行い、常時5人以上の従業員を使用する事業所
| 製造業、土木建築業、鉱業、電気ガス事業、運送業、清掃業、物品販売業、金融保険業、保管賃貸業、媒介周旋業、集金案内広告業、教育研究調査業、医療保健業、通信報道業、士業など |
②国又は法人の事業所
事業主は、社員が入社したときには入社の日か5日以内に、「被保険者資格取得届」等を所轄の年金事務所又は健康保険組合に提出しなければなりません。
労務法令の研修のポイント
労務に関する法令の研修は、以下の点に注意して設計・実施することで、より効果が高く、実務に即した内容とすることができます。
自社の就業規則をベースにする
従業員10人以上の企業では、就業規則の作成が義務となっています。
就業規則は、会社の理念や方針を具体化するため、労働基準法や労務に関する法律の規定を反映したものです。
そのため、自社の就業規則を使って研修を行うことで、より実践的な、企業の実態に即した効果を得ることができます。
なお、就業規則は、必ず必要となる規定以外は、その企業の状況にあわせて修正や追加・削除がされているため、
「なぜ、この規定が必要なのか?」
「なぜ、この規定がないのか?」
を考えさせながら行うことで、より会社の労務を深く理解することができます。
事例等からテーマの拾い出しをする
研修の中でも、とくに参加者の興味を強く引き、記憶に残りやすいのが「自社の事例」を参考にした講義です。
事例のもととなった事実や事件は、通常、多くの方に共有されているため、これを題材にした研修であれば、参加者もより理解しやすいものとなります。
たとえば、
「少し前に、就業規則の変更があった」
「〇〇の現場で事故があった」
などの事例は、研修のテーマとして効果的といえます。
中には、事故を研修のテーマとするのははばかられるという人もいるかもしれません。
しかし、労務管理は労働者の安全・衛生の確保をするためのものですから、同じことを繰り返さないように積極的に取り入れてほしいと思います。
もし、自社の事例について適当なものが見つからない場合でも、「公表されてる同業他社の事例」や「政府が発表している統計値」などを利用することで、リアりてぃのあるテーマ設定をすることができます。
時期やイベントに絞った研修内容にする
労務に関する法律や規則は広範にわたるため、このような講義の内容は総花的となり、また、内容の薄いものとなりやすいといえます。
なので、このような研修は1~2回程度とし、それ以外ではさらに特定の時期やイベントに絞ったテーマで行うことをお勧めします。
例えば、4月に定期採用を予定している会社であれば、「新入社員の労務管理」などをテーマとすれば、これから行う準備や振り返りとなります。
また、労働関係法で禁止されている事項(男女間の賃金差別や違約金など)を取り上げて、自社では問題ないかを検討するのもよいでしょう。
このように、定期的または臨時に発生することが見込まれるイベントや行事に焦点を当てることで、より実践的な研修を行うことができます。
まとめ
企業には、法律により守らなければならないルールがあり、違反した場合には、罰金や社名公表などの罰則もあるため、労務管理の業務は企業の存続を大きく左右するといえます。
そのため、企業は労働者の雇い入れ時だけでなく、その後も定期的に研修を継続し、果たすべき義務や労働者の権利について理解しておく必要があります。
| テストビジネスでは、社内試験問題の作成・実施に関するご相談を承っております。 また、ご希望の方には、正式なご依頼前に無料で見本問題を作成・ご提出するサービスもございますので、お気軽にお問合せください。 |