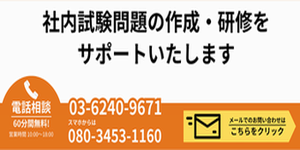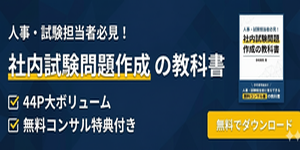なぜ、コンプライアンス研修が必要?するとどう変わる?業種別の最適プランも紹介

現在、コンプライアンスの重要性が増大し、各企業ではその導入や研修が急務となっています。
しかし、コンプライスの範囲は広く、また、必要な知識は企業ごとに異なるため、「何を取り入れればよいのか?」、「仕事にどう生かせるのか?」とお悩みの研修担当者の方も多いと思います。
この記事では、一般的に必要となるコンプライアンス全般に関する知識と業種別の効果的なプラン、研修をするうえで注意すべきポイントについて解説いたします。
コンプライアンスとは?
通常、コンプライアンスは「法令順守」と訳されますが、その範囲は広いため、正しい定義となぜコンプライアンスの理解が必要なのかを理解しておく必要があります。
コンプライアンスの定義
コンプライアンスとは、一般的に「法令順守」を意味します。
「法令」とは、「法律と命令」を合わせた呼称ですが、コンプライアンスはこれよりも広く、社会規範や企業の就業規則、労働契約など、企業が経営をするうえで守るべき規範のすべてを含みます。
しかし、このようにコンプライアンスの具体的な中身は企業ごとに異なるため、研修を行う際には、「自社にとって、守るべきコンプライアンスとは何か?」を明確に定義しておく必要があります。
もし、コンプライアンスが明確でないと?
コンプライアンスを仕事で生かすには、企業や従業員がその基準を自ら理解し、ケースバイケースで適した行動をとれるかが重要となります。
しかし、その定義や具体的な行動基準が明確になっていないと、同じ事例でもそれぞれで異なった対応をしてしまう可能性があります。
また、企業と社員個人が考えるイメージが異なる場合、意思伝達がスムーズにできないばかりでなく、思わぬミスリードを生じる原因ともなります。
そのため、企業はコンプライアンスの定義をするだけでなく、これを全社的に周知し、かつ、研修等を通じて社員に教育や意識づけをすることが重要となります。
コンプライアンス研修をすべき理由
コンプライアンス研修を行うことで、次のような効果を得ることができます。
実務に生かす対応力を獲得するため
企業が従業員にコンプライアンスの遵守とそれを実務で生かすことを求めるのであれば、研修が不可欠となります。
コンプライアンスの研修は、規定や法律を中心としたものとなりやすいですが、その内容を正しく実践するには、それだけでなく、実務に即して対応できるように研修の中身も工夫する必要があります。
事前にリスクを防止するため
何がコンプライアンス違反となるのかを知らないと、ささいな間違えや勘違いから重大な問題を引き起こしてしまうことがあります。
とくに、最近では、SNSによる誤った情報拡散や不適切な投稿により、企業が致命的な損害や評価の低下を引き起こす例も少なくありません。
そのため、研修を通じて、安易な行動や間違いが、どのようなリスクを生じ、また、個人的な責任が生ずるのかを理解してもらう必要があります。
企業価値を向上させるため
通常、企業には商品やサービスの購入者だけでなく、金融機関や行政、株主等と数多くの利害関係者が存在します。
コンプライアンス違反をした場合には、これら利害関係者から責任追及されるだけでなく、社会的にも企業価値を大きく損なうこととなります。
そのため、これからの企業は内向けにコンプライアンス研修をするだけでなく、その行動を広く発信し、利害関係者や社会の理解を取り付けることが求められますます。
企業が取り入れるべきコンプライアンス対応
企業がコンプライアンス対応や研修をするうえで、欠かすことのできない制度や法令としては、以下のようなものがあります。
ハラスメント
令和元年6月5日に女性の職業生活における活躍の推進等に関する法律等の一部を改正する法律が公布され、労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法が改正されました(令和2年6月1日施行)。
また、本改正により、それまで中小企業では努力義務とされていたパワーハラスメントについて、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の「義務」となりました。
今後、企業が適切なハラスメント対応しない場合、会社名が公表されたり、優秀な人材の流失、社会的評価の低下につながる可能性があります。
このようなことを背景として、各種ハラスメントへの対応や研修は、企業がまずはじめに取り組むべきものとなっています。
とはいえ、これらハラスメントとついては、世代の違いによる認識のずれが大きく、とくに高齢者の世代でアップデートされていないことが少なくありません。
したがって、管理者や役員に対しては
▼ ハラスメントの定義や最新の考え方
▼ 自社でハラスメント対策を行う場合の規定の作り方や見直し
▼ ハラスメントの防止の方法
などをテーマとした研修がお勧めできます。
また、一般の社員や関係下請先などに対しては、
▼ ハラスメントとなる具体的な行動
▼ ハラスメントをした場合のデメリット
▼ ハラスメントをされた時の対応や相談
などのテーマで研修をするのがよいでしょう。
個人情報保護法
近年、デジタル技術の飛躍的な進展により、多種多様な形で膨大なデータを収集・利用することができるようになりましたが、悪意のある攻撃や担当者のミスなどにより、重要データの流失が相次いでいます。
とくに個人情報データの流失は、流失の対象となった顧客からの不信感を招くとともに、損害賠償に発展するケースもあります。
また、社内におけるデマや噂話などにより、事実ではない情報が出回り、それが社員の精神的ダーメジとなったり、就業環境や立場の悪化につながることも考えられます。
個人情報を適切に管理・運用するためには、「データガバナンス体制の構築」と「社員等による個人情報の正しい理解」の2点が不可欠となります。
これを実現するには、前者については
・「個人情報の定義や目的の明確化」
・「システム管理・運用上の注意点」
後者については
・「個人情報の発信や取り扱い」
・「プライバシーに対する責任やリスク」
・「SNSによる情報リテラシー」
などの研修が効果的といえます。
著作権・意匠権・商標権
著作権や商標権、特許権などの知的財産権を正しく理解することで、自己の権利を守るとともに、他人の権利侵害やトラブルを回避することができます。
たとえば、自社のHPの中で、権利者の許諾を取らずに著作物等を利用してしまうと、使用の差し止めや損害賠償を請求されるだけでなく、HPの閉鎖という事態にもつながります。
著作権は身近な権利ですが、その分正しく理解していないと大きなトラブルや損失を引き起こしやすいため、コンプライアンスの一部として、「知的財産権とは何か?」、「権利を利用する場合の手続き」などについて担当者レベルから理解しておくのが望ましいです。
なお、著作権の詳しい内容については「次の社内研修で学ばせたい。著作権の基礎知識と許諾がなくとも使えるケース」の記事で詳しく解説しています。
取適法
「取適法」(下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律)は、一定規模以上の会社が物品の製造等の委託をする場合に、発注者と下請事業者間の取引や代金の支払いを規制するものです。
現在の下請法が改正され、令和8年8月1日より「取適法」なります。
下請法では、商品の受領拒否や下請代金の支払遅延、減額などを禁じており、違反した場合には勧告・指導・罰金の対象となります。
主な改正点は、以下の通りとなります。
● 適用基準への「従業員基準」 の追加
● 対象取引への 「特定運送委託」 の追加
● 協議を適切に行わない代金額の決定の禁止
● 手形払等の禁止
取適法の研修では、改正点の他、「禁止される行為の類型」や「実務における対応」をケーススタディで学ぶことが効果的となります。
なお、著作権の詳しい内容については「取適法の追加・改正ポイント解説!」の記事で詳しく解説しています。
関連業法
企業にはそれぞれで関連する法令や規制が定められており、とくに許認可にもとづき事業をしている場合には、業法についての理解は不可欠となります。
しかし、これらの業法には関連する団体の規準や、行政からの通達なども多いため、継続的に知識のアップデートをしないと、気が付かないうちに法令違反や許可違反をしてしまう可能性があります。
したがって、特定の業法だけに偏るのではなく、必要な規準や通達等についてもあわせて学習していくことが重要となります。
各業種別にお勧めの研修プログラム
コンプライアンスの内容は企業ごとに異なるため、業種別の研修を行うことが望まれます。
以下では、業種別にお勧めできる研修プログラムについて解説いたします。
飲食店他接客サービス業
飲食店を中心としたサービス業においては、顧客への対応の他、社員やアルバイトの管理、SNSの利用法、食品衛生に関する知識などが求められます。
また、社員の心身の健康を守るため、カスタマーハラスメントに関する知識や、これにもとづいた対応も重要なテーマとなります。
● 接遇・接客マナー
● 労務管理やカスタマーハラスメントへの対応
● 食品衛生法
● SNSの使い方
製造業
製造業では、製品の品質の保証にもとづく消費者の安全確保の他に、製造現場における労働者の安全確保が大きなテーマとなります。
また、私的独占行為や不公正な取引方法とならないよう、独占禁止法の理解も必要となります。
● 環境基準に関する法令
● PL法(製造物責任者方)
● 独占禁止法
● 労働基準法
● 労災法
卸売・小売業
卸売・小売業においては、従業員の労務管理や店舗運営、宣伝広告に関する知識がポイントとなります。
また、これらの業種では顧客や下請け業者と直接、取引をするケースも多いため、その対応を想定したコンプライアンス研修が望まれます。
● 労働時間の管理
● SNSの利用法や広告の規制
● 店舗運営のルール
● 独占禁止法
● 下請法
建設業
建設業では、建設業法を中心とした知識の理解、労働安全衛生法、労務管理などの他、談合に関する独占禁止法や国土交通省のガイドラインといった研修が重要となります。
また、工事職種が多いため、それらの職種に応じた専門教育も欠かせません。
● 建設業法
● 国土交通省等のガイドライン
● 労災法
● 独占禁止法
● 専門職種に応じた研修
金融業
金融業では、顧客に対する貸付けやリース、金融商品の販売などが中心的なテーマとなります。
そのため、金融商品の取り扱いやセールストーク、財務分析、リスク管理に関する研修が必須となります。
● 銀行法、金融商品取引法その他金融庁の指針や通達
● 個人情報保護法
● 顧客対応やトラブル対応
● ハラスメント防止法
介護業
介護業においては、利用者への接遇やマナー研修、ヘルパーの実務研修などが中心となる他、事務系職員については、介護報酬の算定や請求に関する研修が必要となります。
● 接遇・マナー研修
● ヘルパー実務研修
● 顧客とのトラブル対応や責任
● 介護報酬の算定や請求
● ハラスメント研修
効果的なコンプライアンス研修を行うためのポイント
コンプライアンス研修の内容は、企業の職種や受講者の職位、属性により異なりますが、以下の点を守ることで、より効果的にコンプライアンス研修を行うことができます。
研修の目的の明確化
コンプライアンス研修では、はじめに「会社が守るべきコンプライアンスは何か?」を明確にすることで、経営者と社員が共通の認識を持つことができます。
そのため、研修の事前の準備として、その企業がコンプライアンスをどのようにとらえ、どのように実践していくのかについて、「コンプライアンスプログラムの策定と周知」をする必要があります。
このように、はじめに会社のコンプライアンスの意義や方向性を明確にすることにより、ブレや無駄のない同じ目線の研修を行うことが可能となります。
社内事例を取り入れた研修の実施
どんなに時間をかけて研修をしても、それが実務とかけ離れたものならば、受講者の興味を失わせ、効果の低いものとなってしまいます。
そのためコンプライアンス研修は、単にテキストの内容を読むだけでなく、その企業の業種や業務に関連したものとすることが重要となります。
したがって、コンプライアンス研修は、現場から取り寄せた事例や社員の悩み・希望を取り入れた内容で行うことで、本当にその会社に適した、受講者も興味のわくものとすることができます。
継続的な研修の実施
せっかくコンプライアンス研修をしても、それが1回きりのものであったり、忘れたころに行うものでは、知識の定着はできません。
コンプライアンスは幅広い分野を対象とした研修であるため、それを実務の中で定着させるには、定期的な実施が必要となります。
また、頻繁に法令等も改正されるため、正しく内容をキープするには常に知識をアップデートさせていくことも重要となります。
まとめ
コンプライアンスとは、法令順守を意味しますが、その中には社会常識、マナー、就業規則などの各種規範を含みます。
また、コンプライアンスは、会社が一方的に押し付けるものではなく、その会社や取引先等で働く方の理解と協力があってこそ、業務に生かすことが可能となります。
そのため、効果的なコンプライアンス研修とするためには、「会社にとってのコンプライアンスとは何か?」、「どのような内容のもの?」を「誰に対して行うのか?」を計画して行う必要があります。
| テストビジネスでは、社内試験問題の作成・実施に関するご相談を承っております。 また、ご希望の方には、正式なご依頼前に無料で見本問題を作成・ご提出するサービスもございますので、お気軽にお問合せください。 |