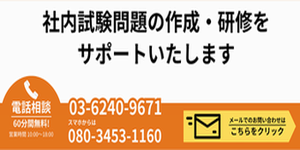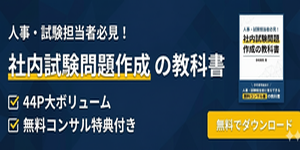補助金・助成金申請のための研修の基礎とポイントについて

現在、国や地方自治体では数多くの補助金や助成金を用意しており、これらを有効に活用すれば、企業の財務や資金繰りに大きなプラスの効果をもたらします。
とはいえ、中には
「補助金や助成金は、難易度が高くなかなか手を出せない」
とお考えの企業も少なくないと思います。
しかし、担当者が補助金等の申請に慣れ、積極的に取り組んでいく環境を整えることができれば、計画的に獲得することが可能となります。
この記事では、補助金と助成金の違い、申請の際のポイント、担当者向けの研修方法について解説いたします。
補助金と助成金の違い
補助金と助成金は、どちらも国等から返還不要で受給できる資金調達の手段ですが、その内容は大きく異なります。
補助金と助成金の区別と相違点
補助金と助成金の法的な違い
補助金や助成金は、一定の事業(補助・助成事業)を行う企業に対し、国や自治体がその経費の一部を資金的に支援する制度です。
補助金と助成金とには、法律上、明確な区別はありませんが、一般的には、次のように分類されています
▼ 補助金
➡ 厚生労働省以外の省庁や団体が行う支援
▼ 助成金
➡ 主に厚生労働省が行うものを指すのが一般的です。
補助金と助成金の主催の目的
補助金は、募集要領により提示される特定の社会的な課題(環境改善や事業の活性化等)について、解決や改善ができるアイデアやスキームを提案できるかどうかが審査や採択の際の重要なポイントとなります。
これに対して、助成金は、主に人の採用や雇用の維持、労働環境の改善などについて行われる給付であるという特徴があります。
また、補助金はコンペ的な形式で行われ、採用されるためには競争と審査があるため、だれもが受給できるわけではありません。
しかし、助成金は決められた要件を満たせば、だれでも受給できるという違いがあります。
| 種 別 | 実施主体 | 受給条件 |
| 補助金 | 主に厚生労働省以外の省庁・自治体が主催 | コンペ形式。審査で採択されないと受給できない |
| 助成金 | 主に厚生労働省が主催 | 一定の要件を満たせば受給可能 |
補助金の申請~受給までの流れ
一般的な補助金・助成金の申請から受給までの流れは、次のとおりとなります。
| 補助金 | 助成金 |
| ① 公募の開始・応募 ▼ ② 内容の審査 ▼ ③ 採択 ▼ ④ 交付決定の通知 ▼ ⑤ 補助事業の開始 ▼ ⑥ 定期検査 ▼ ⑦ 事業の完了および報告書の提出 ▼ ⑧ 確定検査 ▼ ⑨ 最終交付額の確定 ▼ ⑩ 補助金の請求と資金の振込 | ① 公募の開始・応募 ▼ ② 内容の審査 ▼ ③ 採択 ▼ ④ 採択決定の通知 ▼ ⑤ 給付条件の実行 ▼ ⑥ 履行の確認 ▼ ⑦ 助成金の請求と資金の振込 |
以上のように補助金については、受給までに多くのプロセスがあり、審査等にも時間がかかることから、受給までの期間は長めとなります。
これに対して助成金は、プロセスが簡略化されており、必要な条件を満たしていることが確認できれば、短期間で受給できるという特徴があります。
補助金と助成金のメリット・デメリット
補助金と助成金には、返還不要で資金調達ができるというメリットがありますが、デメリットもあるため、これについてもよく考えて申請しないと時間と労力の無駄となってしまう可能性があります。
補助金と助成金申請のメリット
補助金のメリット
🔼 返還不要で資金の調達ができる
🔼 採択されることで、その技術力やビジネスプランが社会的に評価される
🔼 助成金と比較して、利用できる金額の大きいものが多い
助成金のメリット
🔼 返還不要で資金の調達ができる
🔼 厚生労働省の助成金は、必要な要件を満たせれば誰でも受給できる
🔼 補助金よりも、比較的簡単な手続きで申請や受給ができる
補助金と助成金申請のデメリット
補助金のデメリット
▲ 内容の優れたものしか採択されないため、申請しても受給できないことがある
▲ 公募期間が短いものが多い。また、資金の受給までに時間がかかる
▲ 事業者が補助事業にかかる経費の全額を立て替えなければならない
助成金のデメリット
▲ 実施されている数が少ない
▲ 金額が大きくないものが多い
▲ 人の雇用や雇用維持など、対象となる事業の分野が偏っている
補助金を獲得するための必須の確認ポイント
補助金は助成金と比較して、内容が複雑であり、また、審査に通らないと受給できないため、申請は以下のポイントを踏まえて行う必要があります。
補助金の趣旨にあっているか?
補助金は、補助金の趣旨や目的にあった事業に対して支給されます。
そのため、これから行おうとする事業(補助事業)が主催者の求める趣旨や目的に合致したものかどうかということが最も重要となります。
これがずれていると、
「求められるレベルを満たせていない」
「主催者が意図するものと違う内容である」
などとなり、採択の対象がとなります。
したがって、補助金で採択されるには、表面的な要件だけなく、募集要項に書かれている補助金の主旨をしっかり理解し、自分の事業がそれにあったものなのかを確認しておく必要があります。
補助金の難易度に問題はないか?
補助金は、主催する国・省庁等の求めるレベルやテーマにより、採択される難易度に大きな差があります。
そのため、申請にあたっては
「自社でクリアーできる難易度なのかどうか?」
を事前によく検討する必要があります。
通常、助成金は「一定の要件を満たす人を採用する」、「決められた率や額の賃上げをする」などの条件を満たせば受給することができます。
しかし、補助金では、単にモノの購入や人の採用をしただけでは受給できない高度な内容のものも多く、難易度に大きな違いがあります。
そのため、単に補助金が欲しいからといった目先的な理由で申し込むと、結果的に時間も手間も無駄となってしまうこととなります。
したがって、補助金を申請するときには、応募条件や過去の採択事例などを研究し、
「この補助金の難易度はどの程度なのか?」
「自社の実力でクリアーできるのか?」
などを検討しておくことが求められます。
必要な時間を確保できるのか?
補助金の申請は、その内容や条件が難しくなるほど、申請のために多くの時間を要します。
どのくらいの時間がかかるかは補助金の内容により異なりますが、少なくとも1~1.5ヶ月、複雑なものについてはそれ以上の時間がかかると思った方がよいでしょう。
しかし、補助金には、申請期間が短いものも少なくないため、計画的なスケジュールで取り組まないと、時間が足りずに申請書の作成ができない、必要な資料を用意できないということになりかねません。
また、補助金の受給ができた場合でも、その後しばらくの間は、定期報告が必要となるため、これらに対応するための時間や人手も必要となります。
このように補助金の申請では、事業の内容だけでなく、精度の高い申請書を期間内に作成できる体制が整っているかということもポイントとなります。
事業を完了できる資金があるか?
補助金は、そのすべてが「事業主が補助事業にかかる経費を立替払いした後に、補助金を受け取る」仕組みとなっています。
そのため、補助金を受給するためには、補助事業を完了させられるだけの自己資金が必要となります。
補助金の採択がされた場合でも、補助事業を進める途中で資金不足となり事業を完了できない場合には、補助金を受給することはできません。
もし、あらかじめ事業費が不足することが見込まれる場合には、銀行などから融資を受けるなどの対策を講じておく必要があります。
補助金獲得のために担当者がすべきことと研修内容
企業の担当者の方が補助金の申請や補助事業の実施をしていくためには、「補助事業に関する知識」、「補助金申請書の作成スキル」、「税金に関する理解」が必要となります。
補助金制度への理解
補助金の申請をするうえで重要なのは、次の3点です。
| 🔽 自分の補助事業に対する知識 🔽 補助金実施の目的や趣旨への理解 🔽 補助金受給後の税務処理 |
まず、補助金補助金申請担当者は自らが会社を代表して事業を申請をするのですから、当然、その事業について十分な知識を持っていることが求められます。
また、補助金は、主催者がその補助事業を通じて何らかの課題の解決をしたいと考えているのですから、その趣旨や目的が何かを理解し、それにあった事業としなければなりません。
そのため、補助金申請の担当者に強く求められるのが「補助金の募集要項の理解」です。
「募集要項」とは、その補助金等の制度の目的・趣旨・応募条件・禁止事項など、その補助金の申請に必要なすべての事項をまとめたもので、補助金の種類を問わず作成されます。
しかし、申請の経験が少ないと「どこがポイントなのか?」や「具体的にどのような事業ならよいのか?」を読み取ることが難しいといえます。
この点についての能力を鍛えるには、「補助金に関する基礎的な制度や法令の知識」および「実際の募集要領を使った内容の読み方」などが効果的といえます。
| 【研修内容】 ● 補助金に関する基礎的な制度や法令の知識 - 補助金等に係る予算執行の適正化に関する法律 - 補助金適正化法 - 補助金獲得後の税金に関する知識 ● 実際の募集要項を使った内容についての講義 - 小規模事業者持続化補助金第17回公募要領 - 中小企業新事業進出促進補助金公募要領(第1回) ● 受給後の税金の処理(法人税など) |
補助金申請書の作成能力
補助金や助成金は省庁や自治体が独自に行っているため、申請書のフォーマットや記載すべき内容がそれぞれで異なります。
そのため、申請書への記入やアプローチの仕方は、実際の補助金の申請書を使用して学習するのが最適となります。
また、過去に採択された事例に関する申請書の一部が公開されていることもあるため、このようなものも参考となります。
具体的な研修内容としては、申請書の記載方法や書き方についてが中心となりますが、わかりやすく・見やすい申請書とするには、文章の表現力や構築、図形の作成についてもある程度のスキルが必要となります。
【研修内容】
・過去の申請書を利用したアプローチ
・文章の表現方法や構築のスキル
・わかりやすい図形の作成方法のスキル
なお、研修を行う際には、よくある失敗のパターンや実践する際のステップを理解しておくと、効果的に行うことができます。以下の記事では、これらの具体的な手順について詳しく解説していますので、あわせてお読みください。
はじめて補助金申請をする企業のための採択されるポイント
中小企業が補助金の採択されるためには、
🔽 審査の難易度が低めのものぶ
🔽 補助率の大きなものを選ぶ
🔽 事業費の大きすぎないものを選ぶ
という3つのポイントを守る必要があります。
難易度が低めのものを選ぶ
はじめて補助金の申請を行う場合には、難易度の低めの補助金や助成金の申請から始めることをおすすめします。
経験が十分でないのにあまり難しい補助金に手を出してしまうと、
「補助金の趣旨が理解できない」
「申請書の書き方がわからない」
となり、最悪、申請を断念せざるを得なくなります。
しかし、助成金は、必要な要件を満たせば受給でき、また、申請~入金までの時間が短いものが多いため、まずは助成金の申請から行うのもよいでしょう。
補助率の大きなものを選ぶ
各補助金では、どのくらいの補助をするかという「補助率」が定められていますが、その割合は補助金ごとに異なります。
一般的には1/2~2/3というバターンが多いですが、中には3/4や全額といったものもあります。
したがって、補助金を選ぶときには、補助額よりも補助率に注目して選択した方が、より大きな額を受給できることとなります。
事業費の大きすぎないものを選ぶ
補助金では、補助対象額が大きいものが多く、そのため
「補助対象額が大きい = 受給できる額が多い」
という思考になりがちです。
しかし、補助対象額が大きいということは、それだけ立替払いしなければならない額も大きくなるということを意味します。
そのため、あまり受給額にだけ気をとらえられて申請をすると、高い確率で「事業費の不足」を生じることとなります。
また、それと同時に注意したいのが「人件費と設備のバランスの取れたものを選ぶ」ということです。
補助金の中で最も大きなウエートを占めるのは「人件費」と「設備の購入費」です。
けれど、あまりに設備の購入費に偏った申請をすると、「人件費の手当てが間にあわない」、「予定以上の人件費がかかり、本業に支障をきたす」などのトラブルが生じやすくなります。
税金にも注意しよう!
補助金・助成金は、原則、課税
補助金・助成金は「返さなくてよいお金」ではありませんが、税金がかからないわけではありません。
これらは
「法人税(法人)/所得税(個人事業主)」の課税対象
となります。
※ ただし、消費税は非課税となります。
また、課税されるタイミングは、原則として、「受給をしたとき」です。
そのため、事前に準備をしておかないと、翌年度の支払い税額が大きく膨らみ、資金繰りを圧迫する要因となります。
なお、補助金等で設備の購入をした場合には、「圧縮記帳」という税金を繰り延べる制度が利用できます。
通常、補助金を受給した年度は、補助金額が益金扱いとなるため、その年度の法人税が大きくなります。
一方、購入した固定資産は定額法・定率法で処理されるため、あまり大きな額の償却はできません。
つまり、
「(大幅に増えた)益金 - 少額の減価償却費」
となるわけです。
圧縮記帳は、この不利益を軽減するための制度で、補助金を使って固定資産を購入した場合に認められるものです。
圧縮記帳を使うと、翌年度分以降の減価償却費の一部を初年度に先取りして使うことができるため、これにより初年度の減価償却費を大きくすることができます(つまり、初年度の税金を安くすることができる)。
とはいえ、これは税金がなくなったり、安くなるものではありません。
あくまでも翌年度以降の減価償却費の一部を初年度に先取りするだけのため、最終的に支払う税金額は同じとなります。
受給したときは、会計検査にも注意!
補助金の受給をしたときには、会計検査院の検査の対象となります。
会計検査院とは、政府関係機関等の会計を検査する機関で、税務署の調査とは別物となります。
| 会計検査院は、国の収入支出の決算、政府関係機関・独立行政法人などの会計、国が補助金などの財政援助を与えているものの会計などの検査を行う憲法上の独立した機関です。(会計検査院HPより) |
補助金を受給した企業は、この「国が補助金などの財政援助を与えているもの」に該当するため、検査の対象となります。
税務調査が「脱税の有無」を調査するのに対して、会計検査院の検査では「補助金が目的通り、正しく使われているか」を確認します。
そのため、補助事業等の内容や報告に不備・違反がある場合には「補助金の返還」を求められることに注意が必要です。
まとめ
補助金や助成金は返還不要で利用でき、少ない自己負担でその何倍もの大きな事業を行うことができます。
そのため、上手に活用すれば、企業の資金繰り改善に大きく役立ちます。
しかし、補助金等の申請には、事業に対する知識の他、補助制度への理解や申請書の作成・報告などの手続きも必要となるため、企業が補助金等を計画的に獲得するには、担当者の研修が不可欠なものとなります。
| テストビジネスでは、社内試験問題の作成・実施に関するご相談を承っております。 また、ご希望の方には、正式なご依頼前に無料で見本問題を作成・ご提出するサービスもございますので、お気軽にお問合せください。 |