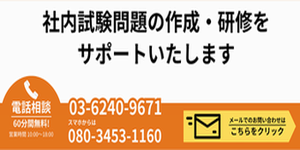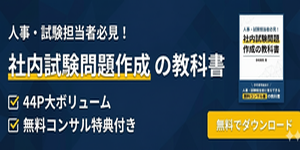社内研修計画作成の手順と抑えておくべき要点

社内研修は、ただ多くの項目をあれこれと詰め込めばよいというものではありません。
はじめに求めるアウトプットを明確にし、その実現のためにどのような手法が有効かという視点で考えることが重要となります。
この記事では、アウトプット型研修をするうえで、必要な目的の設定やアクション、手順のステップについてわかりやすく解説します。
社内の研修計画は「アウトプット」重視で!
研修計画の4つの目的
研修計画では、「なぜ」「誰に」「何を」「どうやって」という目的の設定が重要となります。
これは間違えてしまうと、目指したい目標とその方法との間に、大きなギャップを生ずることとなってしまいます。
| なぜ | 会社が求める知識等の習得、共通理解の形成、技術力の底上げ |
| 誰の | 経営者、全社員、パート、特定の部署、チーム |
| 何を | 会社の理念、就業規則、関係法令、コンプライアンス、ハラスメント |
| どうやって | 集合研修、オンライン研修、ロールプレイ |
アウトプット型研修とは
研修で受講者が積極的に学び、飽きることなく参加できるようにするには、研修の設計段階から工夫をする必要があります。
その際の最大のポイントは、「研修等の知識や成果をアウトプットできるものとなっているか?」ということです。
知識を詰め込むだけの研修は、時間とともに忘れやすいだけでなく、実際の仕事に生かすことも難しくなります。
例えば、次のような例があります。
ある会社では、全社的なコンプライアンス意識を高めるために社内研修を行い、後日、その理解度を図るため確認テストを行いました。
参加者は皆さん真面目に受講し、研修後のテストの平均点も高く、研修担当者も満足する結果となりました。
しかし、その研修は知識偏重のものであったため、本来、求められていた
「何を重視して行動すべきか?」
「どのような判断が求められているのか?」
などについては理解されないままとなってしまいました。
このように研修では、形式的な知識だけでなく、行動や判断に活用できる内容としなければ実務に活かすことが難しくなってしまいます。
アウトプット研修のために必要なアクション
研修で学んだ知識を業務でアウトプットできるようにするには、以下のような設計や仕組みをしておくことが重要となります。
研修目的の設定
効果的で適切な研修を行うためには、
「なぜ、それを行うのか?」
という目的が明確になっていなければなりません。
また、その目的は
「どうやって、アウトプットするのか?」
という、研修後の行動と紐づいたものとなっている必要があります。
会社が研修を行う目的としては、次のようなものが考えられます。
| ● 会社の理念を理解、共感してもらいたい ● 売上げに貢献できるマインドを学ばせたい ● コンプライアンスを理解させたい ● 求める技術要求を満たせるようにしたい ● 優秀な人材を獲得したい |
そしてそれぞれの目的に応じたアウトプットは、次のものとなります。
| 研修の目的 | 求めるアウトプット |
| 会社理念の理解や共感 | 業務全般において臨むべき対応や考え方ができる |
| 売上げ改善のマインド | 販売計画の立て方や効果的な考え方の醸成 |
| コンプライアンスの理解 | 不祥事の防止と根絶、相互理解の促進 |
| 技術力のアップ | 受注の拡大や新製品の開発、不良品発生率の低下 |
このように研修を行う目的はさまざまですが、最終的に得られるアウトプットの内容が異なります。
そのため、研修を行うにあたっては、目的だけでなく「どうやって実現させるのか?」というアウトプットについても併せて考えないと、目的と結果がずれたものとなってしまいます。
対象者の設定
研修の目的や求めるアウトプットラインが決まったら、次に考えるのが「研修の対象」です。
通常、研修の対象者は「職位や職種」または「個人の属性や能力」のいずれかで選定します。
【職位や職種により選ぶ】
| 新人研修 | ビジネスマナー・コンプライアンス・社内規則 |
| 中級者研修 | リーダーシップ・チーム推進・法令等理解力 |
| 管理職研修 | 人材開発・管理能力・財務能力育成・事業計画作成 |
【個人の属性や能力により選ぶ】
プロジェクトリーダー育成・営業力育成、法務や財務担当者育成など
前者は社内における特定の層を対象としたものであるのに対し、後者は個別・限定的な目的に携わる方を対象としたものとなります。
研修を効果的かつ有意義なものとするには、参加者の意識やレベルがある程度揃っていることが望ましいといえます。
これらが揃っていないと、どの程度の研修をすべきなのかがわからないだけでなく、研修後の効果にも大きな開きができてしまいます。
●参加者のレベルのばらつきが大きい
→ 研修レベルの設定が困難、理解度に差
●参加者の意識のばらつきが大きい
→ 受講態度にムラ、積極性にムラ
そのため、研修の受講者の選定では、職位や職種、本人の希望などをベースとしつつも、レベルや意欲によるふるい分けも必要となります。
研修方法の決定
研修は、その実施形式により「集合研修」と「オンライン研修」の2つに大別できますが、その中身によりさらに3つに分類することができます。
【集合研修】
会社や貸会議室などを利用して、対象者をリアルに参加させて行う研修
【オンライン研修】
zoomなどのアプリを利用して、在宅または現場からオンラインで参加させる研修
集合研修とオンライン研修では、以下のようなメリット・デメリットがあります。
| メリット | デメリット | |
| 集合研修 | ・緊張感のある講義となりやすい ・受講者のリアルな反応がわかる ・柔軟な運営がしやすい ・受講者同士のコミュニケーションが生まれる ・作業などの説明に向いている | ・場所や人数に制約がある ・会場や設備の準備が必要 ・会場のレンタル料や受講者の交通費などがかかる ・開催日程が調整しずらい |
| オンライン | ・場所や人数を選ばずに参加できる ・移動時間が不要会場や設備の準備が不要 ・研修にかかるコストを抑えられる | ・受講者の熱意が低くなりやすい ・ネットワーク環境の整備が必要 ・トラブルにすぐに対応しにくいに ・受講者同士の交流が生まれにくい ・作業やロールプレイの説明に向かない |
したがって、人数規模や予算、オンライン体制にもよりますが、以下のような使い分けがよいでしょう。
| 実施に向いた会社 | 実施に向いた研修 | |
| 集合 | ・ある程度の予算がある ・作業やロールプレイが必要な内容 ・参加者が多くない | ・新入社員研修 ・昇進・昇格研修 ・技術職向け研修 |
| オンライン | ・予算が少ない ・文書や画像が中心の内容 ・参加者が多い | ・リーダー研修 ・理念研修 ・知識の習得を目的とした内容 |
アウトプットの決定
研修方法までが明確になったら、次は「どのようにアウトプットするか?」を決定します。
研修の手法にはいくつかの種類がありますが、対象者やアウトプットしたい内容に応じて組み合わせて行うとさらに効果が得やすいものとなります。
| 対象 | 求めるアウトプット | 研修方式 | 研修の内容 |
| 新人 | ビジネスマナーの習得 | 集合研修 | テキストによる講義中心 実際の場面を想定した対応力の育成(ケース問題) |
| 課長 | チームマネジメントの管理力育成 | オンライン | マネジメントの基礎想定問題に関する討議 |
| 営業 | 提案営業力の強化 | 集合研修 | 成功事例の共有 提案営業に関するロールプレイ |
漫然とマナー研修やマネジメント研修とするのではなく、上記のように
▼はじめに求めるアウトプットを明確にする
▼その実現のために有効な手法を考える
とすることで、必要な方法や講義の内容を明確にすることができます。
研修成果の確認
最後に、研修成果の確認をします。
成果の確認は、どのような目的で、どのような研修を行ったかに応じて実施するようにします。
例えば、成果の確認として、後日にペーパーテストを行うでもよいですが、訪問先での場面を想定したロールプレイなどをすると、本当に研修の内容が身についているかを確認できます。
ロールプレイの想定ケース
| 【新人研修】 ● 電話の取次で、正しい対応ができているか? ● 正しい報告書が書けているか? ● 客先での自己紹介等や説明ができているか? 【営業職研修】 ● 成功事例を理解できているかに関するテスト ● 自身の営業方法等に関する討議会の実施 ● 成功者による体験やノウハウに関する発表会 |
以上のように研修は、明確な目標とそれに紐づいたアウトプットをイメージして行うことが重要です。
また、あらかじめこれらをはっきりさせておくことで、「なぜ、その研修が必要なのか?」のビジョンを参加者に伝えられるため、受講者のモチベーションのアップにもつながります。
さらに研修後の効果測定も、当初に設定した目標やアウトプットに沿って行えるため、正しい評価がしやすいとともに、効果が不十分な場合の対策も立てやすくなります。
なお、試験や研修を行う際には、よくある失敗パターンや4つの実践ステップを理解しておくと、さらに充実した内容とすることができます。以下の記事では、これらについて詳しく解説していますので、あわせてお読みください。
まとめ
どのような形式であれ、社内研修で重要なのは、実施側の意思や目標が参加者にしっかりと伝わり、
「なぜその研修を受けなければならないのか?」
「その研修で得られるものは何か?」
が共有されることです。
また、研修計画の作成では、「研修目標の設定」~「研修成果の確認」までのステップを踏まえつつ、さらにこれを効果的なものとするために、まずは経営者が自ら「目的とアウトプットは何か?」をしっかり考えることが重要となります。
| テストビジネスでは、社内試験問題の作成・実施に関するご相談を承っております。 また、ご希望の方には、正式なご依頼前に無料で見本問題を作成・ご提出するサービスもございますので、お気軽にお問合せください。 |