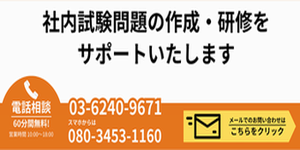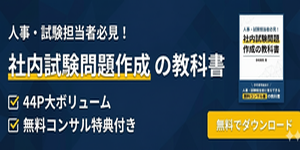次の社内研修で学ばせたい。民法の要点と研修で教えるポイント
会社の研修や昇進試験では、民法に関連する問題を出題する企業は多いと思います。
民法は「私法の王」といわれるほど、生活に密着しており、また、紛争が生じたときの解決基準となります。
しかし、全部で1050条と範囲が広いため、研修などでは、その企業の業種や業務にあった内容を選ぶ必要があります。
この記事では、会社の業務でとくに必要となる「民法の総則~債権編」について、基本的な構成やとくに重要な規定の他、関連する特別法、業種別の出題分野について解説いたします。
民法の構成と概要
民法は、総則・物権・債権・親族・相続編の5つの編により構成されています。以下では、親族・相続編を除く3編について、それぞれ解説します。
総則編(第1条~第174条の2)
民法の「総則編」は、民法の第1編にあたる部分で、すべての私法を対象とした基本的なルールを定めた規定となります。
この総則のルールは、一部の一般法や特別法を除き、すべての私法に適用されるため、民法に限らず私法全般についての、最も規範的かつ基準的なものとなります。
民法総則は、以下の規定で構成されています。
| 第1章 総則 ・通則(第1条・第2条) 第2章 人 ・権利能力(第3条) ・意思能力(第3条の2) ・行為能力(第4条―第21条) ・住所(第22条―第24条) ・不在者の財産の管理及び失踪の宣告(第25条―第32条) ・同時死亡の推定(第32条の2) 第3章 法人(第33条―第84条) 第4章 物(第85条―第89条) 第5章 法律行為 ・総則(第90条―第92条) ・意思表示(第93条―第98条の2) ・代理(第99条―第118条) ・無効及び取消し(第119条―第126条) ・条件及び期限(第127条―第137条) 第6章 期間の計算(第138条―第143条) 第7章 時効 ・総則(第144条―第161条) ・取得時効(第162条―第165条) ・消滅時効(第166条―第169条) |
総則の規定うち、とくに次のものは、日常生活や会社の業務において重要度が高いといえます。
「行為能力」
未成年者や単独では有効な契約等をすることのできない成年被後見人などについた定めた規定です。
これらの者が契約をした場合の効果や有効性を判断するのに重要な基準となります。
「法人」
条文数は少ないですが、法人が有効に成立するための要件や、行うことのできる行為の範囲を規定しています。
「物」
不動産と動産の区別、不動産に法律的に従属するもの、果実(果物や家賃など、そのものから生ずる利益)について定められていることから、とくに不動産関連の業務では重要な規定となります。
「公序良俗」や「心裡留保」、「虚偽表示」、「錯誤」
他人に表示した意思(意思表示)がどのような場合に無効となるかについての規定です。
当事者以外の第三者が関係する場合の効果を定めていることから、契約関連において重要となります。
「詐欺又は強迫」
意思表示が取り消しとなる場合の規定であり、行った契約を取り消すことができる場合の要件を定めた規定となります。
「意思表示の効力発生時期等」
相手に向けてした意思表示がいつからその効力を生じるかについて定めたもので、郵便やメールなどの通知が届いた、届いていないという争いの場合に、その基準となります。
「代理」
個人や法人が代理人を通じて行った意思表示の効果やその範囲、無権限で行った場合の効果等について定めた規定です。
とくに会社が社員を通じて他人へ行った行為が有効か無効かを判断するうえで重要となります。
「無効・取り消し」
無効と取り消しの効果の違いや、無効となった場合の原状回復義務などについて定めています。
そのため、契約が取り消し・無効となった場合に、相手に請求できる返還の義務やその範囲を判断するときに役立ちます。
「期間の計算」
いつから期間が始まり、終了するのかを定めているため、契約期間を定める場合に重要な規定となります。
「時効」
物や権利を保有するだけで所有権等を得たり、逆に失ったりする制度について規定したものであり、とくに消滅時効は権利の喪失にかかわるものなので業務においても重要となります。
物権編(第175条~第398条の22)
民法の「物権編」は、民法の第2編にあたる部分で、物権とは物を直接的に支配し、所有、使用、収益、換価する権利です。
この物件編で規定されたものだけが物権として効力を持ち、登記することで第三者に対してもその権利を主張することができます。
民法物権編は、以下の規定で構成されます。
| 第1章総則(第175条―第179条) 第2章 占有権 ・占有権の取得(第180条―第187条) ・占有権の効力(第188条―第202条) ・占有権の消滅(第203条・第204条) ・準占有(第205条) 第3章 所有権 ・所有権の限界 ・所有権の内容及び範囲(第206条―第208条) ・相隣関係(第209条―第238条) ・所有権の取得(第239条―第248条) ・共有(第249条―第264条) 第4章 地上権(第265条―第269条の2) 第5章 永小作権(第270条―第279条) 第6章 地役権(第280条―第294条) 第7章 留置権(第295条―第302条) 第8章 先取特権 ・総則(第303条―第305条) ・一般の先取特権(第306条―第310条) ・動産の先取特権(第311条―第324条) ・不動産の先取特権(第325条―第328条) ・先取特権の順位(第329条―第332条) ・先取特権の効力(第333条―第341条) 第9章 質権 ・総則(第342条―第351条) ・動産質(第352条―第355条) ・不動産質(第356条―第361条) ・権利質(第362条―第368条) 第10章 抵当権 ・総則(第369条―第372条) ・抵当権の効力(第373条―第395条) ・抵当権の消滅(第396条―第398条) ・根抵当(第398条の2―第398条の22) |
このうち、とくに次の規定は、日常生活や会社の業務において重要性が高いといえます。
「占有」
物を所持しているだけで行使できる権利であり、その内容には複数の種類があります。
また、占有権に基づく訴えは日常や業務でも活用することができます。
「所有権」
万能の権利ですが、条文のほとんどが隣接地所有者との関係を規定した「相隣関係」や、複数人で所有する場合の「共有」の規定となっています。
このうち、とくに共有は、購入や相続により他人と権利を共同で持つ場合の規定のため、日常生活に密着したものとなります。
「抵当権・根抵当権」
普通抵当と根抵当権の2種類があり、どちらも不動産等を担保にするという点では同じですが、その内容は大きく異なります。
住宅ローンのように一回きりの担保については抵当権が規定しますが、商取引や銀行取引のように一回の契約(基本契約)で何度も借り入れ・返済を繰り返すような場合には、根抵当権の対象となります。
銀行や取引先との間での融資や借り入れをする際の担保設定について、欠かせない規定となります。
債権編(第399条~第724条の2)
民法の「債権編」は、民法の第3編にあたる部分で、債権とは特定の人に特定の行為や給付を請求できる権利です。
債権は物権とは異なり、特定の相手にのみ効力を持つ権利ですが、契約の大半は債権であるため、日常生活や会社の経営において非常に重要な役割を果たします。
民法債権編は、以下の規定で構成されます。
| 第1章 総則 第1節 債権の目的(第399条―第411条) 第2節 債権の効力(債務不履行の責任、債権者代位権、詐害行為取消権 第412条~第426条) 第3節 多数当事者の債権及び債務(総則、不可分債権及び不可分債務、連帯債権、連帯債務、保証債務 第427条~第465の10条) 第4節 債権の譲渡(第466条~第469条) 第5節 債務の引受け(併存的債務引受、免責的債務引受 第470条~第472条の4) 第6節 債権の消滅(弁済、相殺、更改、免除、混同 第473条~第520条) 第7節 有価証券(指図証券、記名式所持人払証券、その他の記名証券、無記名証券 第520条の2~第520条の20) 第2章 契約 第1節 総則(契約の成立、契約の効力、契約上の地位の移転、契約の解除、定型約款 第521条~第548条の4) 第2節 贈与(第549条~第554条) 第3節 売買(総則、売買の効力、買戻し 第555条~第585条) 第4節 交換(第586条) 第5節 消費貸借(第587条―第592条) 第6節 使用貸借(第593条―第600条) 第7節 賃貸借(総則、賃貸借の効力、賃貸借の終了、敷金 第601条~第622条の2) 第8節 雇用(第623条―第631条) 第9節 請負(第632条―第642条) 第10節 委任(第643条―第656条) 第11節 寄託(第657条―第666条) 第12節 組合(第667条―第688条) 第13節 終身定期金(第689条―第694条) 第14節 和解(第695条・第696条) 第3章 事務管理(第697条―第702条) 第4章 不当利得(第703条―第708条) 第5章 不法行為(第709条―第724条の2) |
このうち、とくに以下の規定は、日常生活や会社の業務において重要となります。
「債権の目的」
このうち、特定物の引き渡しの注意義務や金銭債権、法定利率は、契約の主要な要素について定めたものとなります。
そのため、業務で契約書の作成や管理をする方にとっては必ず知っておくべき規定となります。
「債権の効力」
履行期と履行遅滞、履行不能、損害賠償、金銭債務の特則などが定められていることから、どのような場合に契約が不履行となり、どのくらいの損害を請求できるかなどを判断する際に役立ちます。
「債権者代位権」
「債権者代位権」は、自分の債権を回収するため他人の権利を相手に代わって行使できる権利です。
とくに、相手が登記手続きに協力しない場合などには、強制的に従わせることが可能となります。
「連帯債務と連帯保証」
これらは、借入れの際に複数の債務者や保証人に連帯して責任を負わせる契約手法です。
法人の借入れで代表者が連帯保証人となった場合に、どのような責任が生じるのかや、他の債務者にどのような請求ができるのかを理解するうえで重要な規定となります。
「債権譲渡」
自分が保有し、または保有される債権が譲渡された場合の効果を定めた者です。
だれに対して請求や支払いをすべきかや優先順位を定めているため、法的に正しい相手先や手続きをするうえで必要な規定となります。
「弁済」
弁済は、自分が行った弁済がどのような場合に有効となるのかや、証書の取り扱いなどを規定しているため、企業間での支払いに関するトラブルの防止に役立ちます。
「相殺」
相殺は、自分が相手に対して債権(反対債権)を有する場合に、その額を帳消しにする規定です。
これを活用することで、相手に支払いの資力がない場合でも、実質的な回収を図ることができます。
「契約の効力」
この中では、同時履行の抗弁権や債務者の危険負担、契約の解除の規定が重要となります。
その中でも契約の解除は、通常の取引の中で多く利用されるため、正式な解除をするために知っておくべき規定といえます。
「売買」
債権編の中でも、最も取引数が多い売買について定めています。
また、売買の中でも追完請求権(以前の瑕疵担保請求権)に関する規定は、売買におけるトラブルの処理において、重要な判断の基準となります。
「消費貸借」
通常、金銭の貸し借りは、金銭消費貸借となります。
ここでは、金銭消費貸借の成立要件などを規定しているため、融資や貸付けの契約をする際には中心的な規定となります。
「賃貸借」
借賃を支払って家や建物などを借り受ける場合の内容を規定する規定です。
しかし、実際の取引では、借地借家法などの特別法が優先的に適用されるため、それらもあわせて理解しておく必要があります。
「雇用」
他人を雇うときの基本的な契約となりますが、これについても実際の人の雇用については、労働基準法が優先して適用されるため、こちらについての理解も不可欠となります。
「請負」
制作を依頼した建物や製品に不具合があった場合に追加で補修を請求したり、契約の解除ができることを規定されているため、業務で請負契約を行う場合には必ず理解しておくべき規定となります。
「委任」
委任は、他人に業務などを依頼する場合に適用される規定であり、仕事でコンサルや士業に対する委託をする場合の契約の基本となる規定です。
「不法行為」
故意または過失により他人に損害を与えた場合の処理に関する規定です。
自動車事故や企業活動において生じるトラブルの賠償の基準を定めているため、ぜひとも押さえておきたい知識となります。
民法に関連する特別法
特別法とは、広く全般に適用される一般法よりも優先して適用される法律のことをいいます。
民法には特別法がいくつもあり、その中には強行規定(違反すると無効になるもの)も数多く存在します。
そのため、企業における研修や問題作成のためには、これらについても理解しておく必要があります。
借地借家法
借地借家法は、建物の所有を目的とする地上権・土地賃貸借(借地権)と、建物の賃貸借(借家権)について定めた特別法です。
民法の賃貸借の条文の特別法となるため、こちらが優先して適用されることになります。
民法よりも借主の権利が大幅に強化されており、また、「強行規定に抵触する内容の契約で借主に不利なものは無効」となることに注意が必要です。
消費者契約法
消費者契約法は、事業者と消費者の契約関係を規律する法律で、民法の契約条文の特別法となりますが、「消費者と消費者」または「事業者と事業者」の間の契約には適用されません。
なお、消費者契約法に反する契約は、無効または取り消しの対象となります。
特定商取引法
特定商取引法は、事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止する法律です。
訪問販売や通信販売等の一定の取引類型を対象とした、民法の契約条文の特別法となります。
特定商取引法違反の行為は、クーリング・オフの対象となる他、行政処分や刑事罰の対象にもなります。
労働基準法
労働基準法は、労働者に適用される労働条件の最低ラインを定めた法律で、民法の契約や請負条文の特別法となります。
労働基準法に違反した行為は無効となる他、労働基準監督署による行政処分の他、悪質なものについては刑事罰が科されます。
また、違反の内容によっては事業主も罰せられます。(両罰規定)
労働契約法
労働契約法は、労働者と使用者の間の労働契約の成立や内容、終了などに関する規定を定めた法律です。
これに違反した場合の罰則はありませんが、契約が無効となったり、労働基準監督署による行政処分の対象となります。
取適法
取適法(中小受託取引適正化法)は、下請事業者に対する親事業者の不当な取り扱いを規制するものです。
以前は下請法と呼ばれていましたが、改正により取適法となりました。
これは民法の請負条文の特別法となりますが、ケースによっては独占禁止法が適用される場合もあります。
下請法に違反した行為は、公正取引委員会等による勧告の他、罰金刑の対象となります。
なお、最新の取適法について詳しく知りたい方は「取適法の追加・改正ポイント解説!」の記事をご参照ください。
PL法
PL法とは、製造物責任法を意味し、製造物の欠陥により損害が生じた場合の賠償責任を定めた法律です。
民法の不法行為責任条文の特別法であり、製造業者だけでなく、加工、輸入した者なども対象となります。
製造物により他人の生命・身体・財産に損害が生じた場合には、「無過失」でも生じた損害を賠償する責任を負います。
会社法
民法が一般法であるのに対し、会社法は商取引に関する特別法となります。
そのため、会社間における契約や取引については、民法に優先して会社法が適用されます。
独占禁止法
独占禁止法は、企業による私的独占や不当な取引制限など、公正・自由な活動を妨げる行為を規制する法律です。
民法の契約や請負条文の特別法であり、この法律に違反した場合は、公正取引委員会等から勧告などの行政処分の他、刑事罰が科せられます。また、違反の内容によっては事業主も罰せられます。(両罰規定)
なお、建設業の方で、談合と独占禁止法について詳しく知りたい方は「談合をなくしたい建設業が知っておきたい独占禁止法の知識」の記事をご参照ください。
その他の法律
民法の特別法ではありませんが、一定の分野において一定の行為をする場合の制約を定めた法律があります。
これらが民法と抵触するときは、これらの法律が優先して適用されます。
例:建設基準法、建設業法、労働者派遣法、食品衛生法、景品表示法、金融商品取引法、利息制限法、消費生活用製品安全法、電気用品安全法など
業種別におすすめ!問題出題や研修に必要な法律
社内試験の問題や研修において、どのような法律が必要となるかは、企業の業種や取り扱う業務により異なります。
以下では代表的な業種につき、必要となる民法の規定と特別法についてご紹介します。
業種全般に共通して必要となる条文や知識
▼ 民法(契約・売買・不法行為 -など)
▼ 会社法
▼ 労働基準法
飲食業・小売業
<飲食業>
▼ 食品衛生法
▼ 風適法(酒類の提供 )
▼ 食品リサイクル法
<小売業>
▼ 特定商取引法
▼ 景品表示法
▼ 特定商取引法
建設業
▼ 建設業
▼ 独占禁止法
▼ 建築基準法
▼ 建設業法令遵守ガイドライン
製造業
▼ PL法
▼ 取適法
▼ 独占禁止法
▼ 環境関連法令
金融業
▼ 銀行法
▼ 金融商品取引法
▼ 保険業法
▼ 貸金業法
▼ 金融庁ガイドライン
介護業
▼ 介護保険法
▼ 消防法
▼ 高齢者虐待防止法
まとめ
民法はすべての私法のもととなる重要な法律です。
また、関連する特別法も多く、その中には強行規定もあるため、これらについてもあわせて理解していく必要がありますが、これらすべての規定を理解するには多大な時間と労力を要します。
そのため、社内試験問題の作成や研修をする際には、「自分の会社や業務に必要な民法や特別法は何か」を考え、絞り込むのが効率的といえます。
| テストビジネスでは、社内試験問題の作成・実施に関するご相談を承っております。 また、ご希望の方には、正式なご依頼前に無料で見本問題を作成・ご提出するサービスもございますので、お気軽にお問合せください。 |