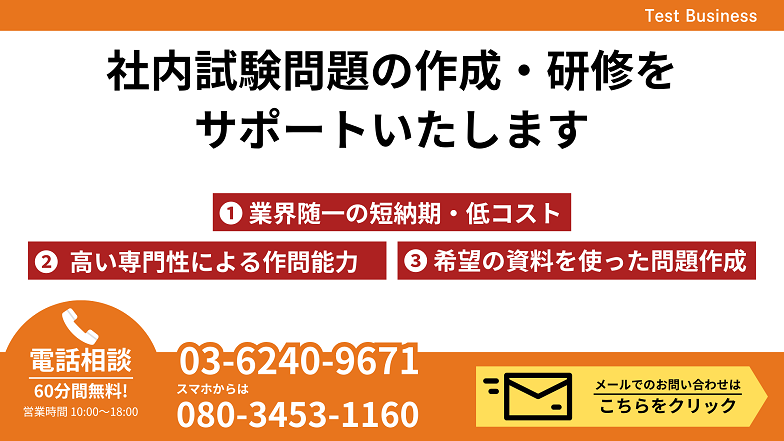社内試験問題見本1
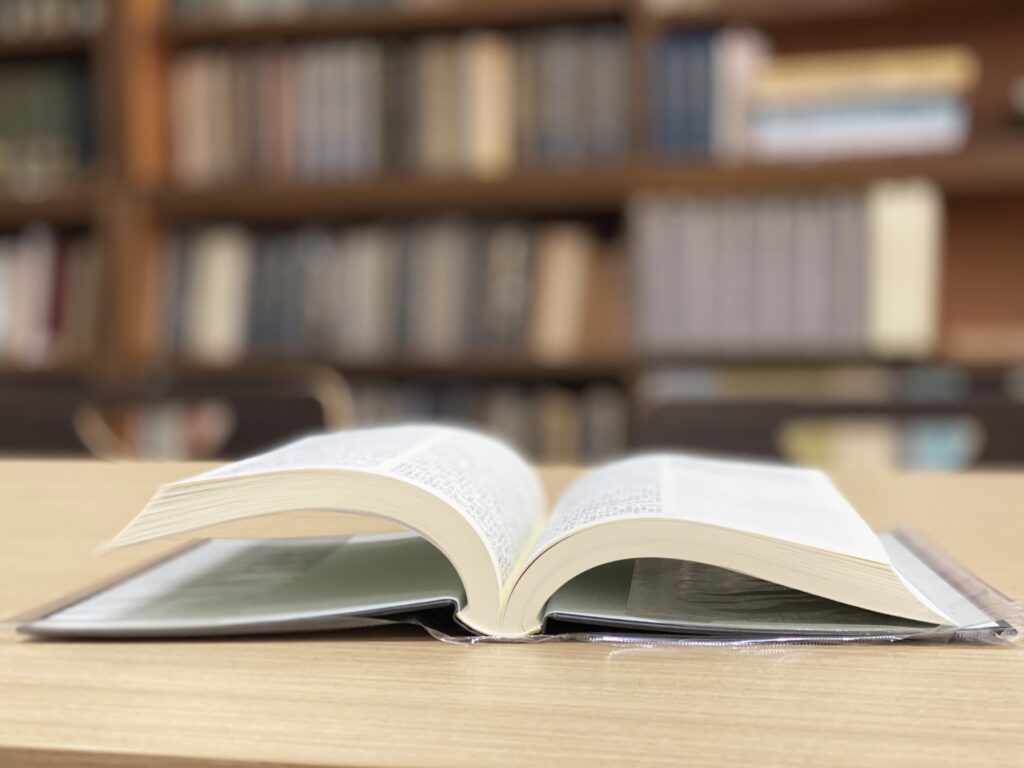
以下では、よく社内試験に出題される問題の見本の一例を掲載しましたので、自社の問題作成の参考にお役立てください。
※「社内試験問題その2」についてはこちら
| 社内試験問題見本その1 | 一般教養 経営分析 マナーその他 |
| 社内試験問題見本その2 | マーケティング 法律 コンプライアンス 5S マネジメント(ドラッガー) 内部統制 |
一般教養
問 2023年10年1日より、消費税の新しい仕入税額控除の方法として適格請求書等保存方式「 」が開始された。
正解 インボイス
問 国内総生産とは、「居住者たる生産者による国内生産活動の結果、生み出された付加価値の総額」のことである。これは通称「 」と略して呼ばれることが多い。
正解 GDP
問 ハインリッヒの法則は 労働災害における経験則の1つで、1つの重大事故の背後には「 」の軽微な事故があり その背景には 300 の異常が存在するというものである。
正解 29
問 以下の①~④の日本語のことわざに最も似た意味の英文を次の(ア)~(エ)の中から選び答えよ。
①:『捨てる神あれば拾う神あり』 ②:『郷に入っては郷に従え』 ③:『思い立ったが吉日』 ④:『鬼の居ぬ間に洗濯』
(ア):“When the cat’s away, the mice will play.”
(イ):“When one door shuts, another opens.”
(ウ):“When in Rome, do as the Romans do.”
(エ):“There is no time like the present.”
正解 ① イ ② ウ ③ エ ④ ア
問 ビジネスマナーに関する説明として以下の①~④のうち、正しいものを選べ。
① お客さまとエレベーターに乗る際には、お客様が出入りしやすいよう、自分が奥へ控えるようにする。
② 「言う」の尊敬語は「おっしゃる」、謙譲語は「申し上げる」である。
③ お客様を案内する際には、お客様がわかりやすいようお客様の正面に立って先導するよう心掛ける。
④ 応接室における席次は、原則、「出入口から遠いほど下座」となるので、お客様の席はできるだけ出入口付近となるようにする。
正解 ②
問 売上原価とは、その売上をつくるのに要した商品の原価の合計であり、期首在庫高(原価)に、期中に入ってきた商品の「 」を足し、そこから期末在庫高(原価)を引いて求める。
正解 仕入原価
問 以下の文章につき、選択肢の中から正しいものを選び、それぞれ答えよ。
「令和6年4月1日「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(改善基準告示)による「自動車の運転の業務に主として従事する」とは、(ア)又は人を運搬するために自動車を運転する時間が現に労働時間の(イ)を超えており、(ウ)当該業務に従事する時間が年間(エ)時間の(イ)を超える場合が対象となる。」
| ① かつ ② 総労働 ③ 又は ④ 半分 ⑤ 荷物 ⑥ 3分の2 ⑦ 物品 ⑧ 総出勤 |
正解 (ア)⑦物品 (イ)④半分 (ウ)①かつ (エ)②総労働
財務・会計
問 流動資産に関する記述につき、以下の①~④のうち、正しいものを選べ。
① 流動資産と固定資産化の区別は、すべて「1年基準」で決定される。
② 貸倒引当金は、売上債権についてマイナスで表示される。
③ 製品・商品以外の売却代金の未収分は、「売掛金」として処理される。
④ 原材料・製品・売掛債権、消耗品は、棚卸資産に分類される。
正解 ②
問 各利益の特徴に関する記述として、以下の①~④のうち誤りを選べ。
① 売上総利益は、企業の商品の消費者への訴求力や製造活動の効率性を表す利益である。
② 営業利益は、企業の一定の経営成果を表す利益である。
③ 経常利益は、総合的な企業の収益力を表す利益である。
④ 当期総利益は、経常的な損益項目を加減した利益である。
正解 ④ 当期総利益は、非経常的な特別損益項目を加減した利益である。
問 各利益の特徴に関する記述として、以下の①~④のうち誤りを選べ。
① 売上総利益は、企業の商品の消費者への訴求力や製造活動の効率性を表す利益である。
② 営業利益は、企業の一定の経営成果を表す利益である。
③ 経常利益は、総合的な企業の収益力を表す利益である。
④ 当期総利益は、経常的な損益項目を加減した利益である。
正解④ 当期総利益は、非経常的な特別損益項目を加減した利益である。
問 会計に関する基本説明として以下の①~④のうち誤りを選べ。
① 株式の所有権を細かく分けたものを株式といい、株式を持っている人を株主という。
② 会社が資金調達をする方法には、銀行等からの借入れによる間接金融と、株式や社債の発行による直接金融の方法がある。
③ 支出を将来の収益に対応させるために、支出した資産の額を計上したものからそれに応じた償却を行うことを減価償却といい、これにより現金が流出する。
④ 流動比率とは、流動資産を流動負債で除して求められる指標であり、200%以上が望ましいとされる。
正解 ③ 減価償却は現金の流出を伴わない
問 以下の自己本比率に関する説明につき、( A )と( B )に入る語句をそれぞれ答えよ。
自己資本比率とは自己資本を( A )で除して求められる指標であり、会社の負債額が2億円、自己資本額が3億円の場合の自己資本比率は( B )%となる。P243
正解 A:総資産 B:60
問 流動資産600、固定資産500、流動負債300、固定負債450の場合の自己資本の額は( )となる。
①350 ②450 ③550 ④600
正解 ①
会計に関する説明として、以下の①~④のうち誤りを選べ。
① キャッシュフロー計算書は、「会社のお金が何によってどれだけ増減したか」を読み取りやすいように組み替えて表にしたものである。
② 子会社とは、ある会社が影響を及ぼしている会社であり、関連会社とは、ある会社に支配されている会社である。
③ 時価会計とは、金融資産と金融負債のうちの一部を期末の時価に基づいて評価する会計方法をいい、この場合の時価とは公正な評価額のことであり、合理的に算定できる金額を含むものである。
④ 有価証券については、将来売る予定のあるものだけが時価評価の対象となる。
正解 ②
問 キャッシュフローに関する説明として、以下の①~④のうち誤りを選べ。
① 貸借対照表はお金のストック情報であるのに対して、キャッシュフロー計算書はお金のフロー情報を表すものである。
② 資金繰り表が会社のお金が不足しないように管理するものなのに対して、キャッシュフロー計算書はお金の増減を明らかにすることで事業の構造を把握する役割を持つ。
③ キャッシュフロー計算書以外でも、貸借対照表の現金勘定科目を見ることでお金がどれだけ増減したかを知ることができる。
④ 損益とキャッシュは、計上されるタイミングが異なるが、最終的な損益とお金の増減は一致する。
正解 ③
問 以下の①~④のうち誤りを選べ。
① 現金300万円を元手に会社を設立した際の仕分けは、「現預金300/資本金300」となる。
② 損益計算書で算出された当期純利益は、貸借対照表の利益剰余金として計上されるが、これは貸借対照表と損益計算書の勘定科目をつなぐ唯一の接点といえる。
③ 商品を300万円で売却したが、200万円は現金で回収し、残額の100万円は翌月末回収の約束をした場合の仕訳は「現金200万円・未収金100万円/売上高300万円」 である。
④ 新株予約権とは、権利者が株式会社に対して行使することにより、会社の株式の交付を受けることができる権利であり、新株予約権を無償で発行するものをストックオプションという。
正解 ③
問 以下の①~④のうち、誤りを選べ。
① 仕入れたが売れなかった商品や、作ったが売却できなかった製品に対応する原価部分は、会計上の原価として費用計上することはできず、在庫として資産に計上されるため、このようなものが多いと利益を圧迫する。
② 特別損失とは、土地の売却損、在庫の破棄損、災害による損失などその事業年度だけの臨時項目でかつ巨額の特別な損失をいい、これが多い場合には、最終的に当期純利益の減少となる。
③ 当期純利益額が同じであっても、在庫や売掛金が増加すると、自己資本利益率は低くなり、総資産利益率は高くなる。
④ 売上総利益とは、いわゆる粗利を意味し、売上総利益が同業他社に比べて低い場合には、商品原価のかけすぎが原因であるため、仕入先や原料の見直しを検討する必要がある。
正解 ③
問 次の企業の財務資料にもとづき、各問いの空欄に当てはまる数字を記入しなさい。(単位:百万円)
貸借対照表
| 資産の部 | 負債の部 | ||
| 現金預金 | 1,100 | 買掛金 | 1,600 |
| 売掛金 | 2,100 | 支払手形 | 1,300 |
| 受取手形 | 1,500 | 短期借入金 | 800 |
| 有価証券 | 1,000 | その他流動負債 | 500 |
| 商品 | 1,200 | 長期借入金 | 1,300 |
| 固定資産 | 2,600 | 純資産の部 | |
| 資本金 | 2,800 | ||
| 利益剰余金 | 1,200 | ||
| 資産合計 | 9,500 | 負債・純資産合計 | 9,500 |
損益計算書
| 売上高 | 8,800 |
| 売上原価 | 5,000 |
| 販売費及び一般管理費 | 3,100 |
| 営業外収益 | 400 |
| 営業外費用 | 200 |
| 当期純利益 | 300 |
キャッシュフロー計算書
| 営業活動によるキャッシュフロー | 900 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | |
| 財務活動によるキャッシュフロー | -400 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,100 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,500 |
① この企業の営業利益は、( )百万円である。
正解 700
② この企業の売上高経常利益率は、( )%である。
正解 10.2
③ この企業の当座比率は、( )%である。
正解 135.7
④ この企業の在庫回転率は、( )回である。
正解 4.2
⑤ この企業の固定長期適合率は、( )%である。
正解 49.1
⑥ この企業の投資活動によるキャッシュフローは、( )百万円である。
正解 100
⑦ この企業のキャッシュフローマージンは、( )%である。
正解 10.2
経営分析
問 各種指標に関する説明として以下の①~④の内、正しいものを1つ選べ。
① 「総資本回転率」は、会社が運用している総資本が売上に換算してどのくらい回転したかを表すものであり、 この数値が高いほど上手に資本を運用しているといえる。
② 自己資本比率は 自己資本を総資本で除して得られる比率であり、この自己資本には出資金と利益剰余金を含む。
③ ROAは会社の経営が長期的観点から見て順調であるかどうかを総合的に判断する指標の一つであり、税引き後利益を総資本で除したものとなる。
④ 当座比率は当座資産を流動負債で除して得られる比率であり、100%以上あれば優良とされる。
正解 ③
問 減損会計に関する説明につき、以下の①~④のうち誤りを1つ選べ。
① 「減損会計」は、減損の事実を認識することにより固定資産の帳簿価格を期末に現在の評価価格まで下げる会計処理である。
② 減損会計では、対象となる固定資産につき減損の有無をチェックし、将来、その資産が生み出す利益が帳簿価格を下回っていれば減損の対象とする。
③ 減損会計の対象となるのは、事業用設備やゴルフ場、遊休地などの収益力や市場価値が低下した事業用固定資産であるため、企業買収により生じたのれんなどの観念的な価値は含まれない。
④ 減損が生じた場合の具体的な処理は、帳簿価格から現時点の資産価値を差し引いて損失を計上することにより行う。
正解 ③
問 経営分析に関する説明につき、以下の①~⑤のうち誤りを選べ。
① 一般的に決算書と呼ばれる書類は、会社法では計算書類あるいは計算書類、金融商品取引法では財務諸表と使い分けられるが それらを構成する書類はいずれも同じものである。
② 貸借対照表の純資産の部の資本剰余金と利益剰余金は、どちらもこれまでの会社の利益が累積されたものである。
③ 損益計算書の経常利益を見れば、その会社が本来の活動からどのくらいの利益を獲得しているかを推察することができる。
④ 貸借対照表と損益計算書はそれぞれが異なる科目で作成されるため、この2つをつなぐ接点はない。
⑤ 有形固定資産の取得による支出は投資活動、社債の発行による収入は財務活動によるキャッシュフローに分類される。
正解 ⑤
問 以下の損益分岐点の計算式について、( A )~( C )に入る数値をそれぞれ答えよ。
( A ) 変動費 固定費
------------- :変動費率 = -------------- ( B ) = -------------
1-変動比率 売上高×100 1- 変動費
--------
( C )
正解 ( A )固定費 ( B )損益分岐点売上高 ( C )売上高
問 財務諸表分析に関する記述につき、誤りを選べ。
① 財務諸表分析の基本は「経済性による比較分析」である。
② 自己本利益率は、売上高当期純利益率、総資本回転率、財務レバレッジに分解できる。
③ 自己資本比率で計算される自己資本には、他人資本を含む。
④ 債務返済比率は、「債務返済額/税引き後利益」で表される。
正解 ③
マナーその他
問 適切な在庫管理を進めるうえで重要なポイントに関する説明につき、誤りを選べ。
① 適品であること
② 適量であること
③ 適所であること
④ 適質であること
⑤ 適時であること
正解 ④ 適質 → 適価
問 棚卸に関する説明として以下の①~④につき、誤りを選べ。
① 棚卸の参加者の目で見て、不良品や不活動商品を発見し、記録する。
① 棚卸では、決められた一定時点における実在庫の実数を正しく数えて、棚卸数を確定する。
② 確定された棚卸数と経理の帳簿在庫数を照合して、差異がないかを確認する。
③ 差異が是正されなかった実在庫品は、棚卸数を経理の帳簿数にあわせて変更し、調整する。
正解 ④
問 以下の提案営業に関する説明において、( A )と( B )に入る語句をそれぞれ答えよ。
「提案営業をする上では、担当者が顧客の課題について理解できている必要があるが、顧客理解を深めるには担当者自身が自分自身の( A )を高めることや、どの程度の需要(売上げ見込み)が得られるかの予測やそれに応じた( B )が必要となる。
また、それとともに、顧客の意思決定プロセスがどうなっているかを知ることも重要なポイントとなる。」
正解 ( A ) 問題意識 ( B ) 資源配分
問 プレゼンの進め方に関する説明につき、誤りを選べ。
① プレゼンが終わった時に顧客をどのような状況に導くのかを想定しておくことで目的の設定を明確にすることができる。
② プレゼンを立案する際には、プレゼンの終了時に相手方にどのような意思決定をしてもらうかを考えて行う必要がある。
③ 最近の研究では 人間の短期 記憶の限度は3から5個とされているため ポイントは4個程度に絞り込むのがよい。
④ プレゼンは資料の出来栄えや説明者の伝え方が重要であるため、相手についての情報はできるだけ意識しない方がよい。
正解 ④
問 以下の文章につき、( )に入る語句をそれぞれ答えよ。
情報の整理では、「情報の( A )」、「情報の即時化」、「情報の( B )」の3つの大きな原則があり 、( A )して情報を整理・分類し、即時に頭にファイルし、活用できるように( B )することが重要となる。また、すぐに情報を活用するには、ファイルする情報収集( C )をなるべく少なくすることや、( D )化してすぐに取り出せるようにしておくことが大切といえる。
正解 ( A )規格化 ( B )集中化 ( C )道具 ( D )活字
問 OJTに関する説明につき、誤りを選べ。
① これまでOJTは企業内教育の基本として数多くの企業で行われてきたが、最近では
成果主義の導入や人材の流動化に伴い、従来のやり方の見直しが進められている。
② 企業内教育の3基本型として捉えられていたOJT、OFF-JT、自己啓発について
は、近年では自己啓発の比重が高まっている。
③ これからのOJTでは、能力開発を背景とした自己啓発にもとづき、その結果として企
業の目標達成に貢献するあり方が求められている。
④ OJTの目的は、上司が職場内で仕事を通じて部下を指導・育成していくための教育研
修であるため、仕事に必要な知識・技能・マナーに限定して行うべきである。
正解 ⑤
問 企業内教育の位置づけの説明として( )に入る語句を答えよ。
これまでOJTを通じて多くの人間が携わってきた仕事から学び、吸収してきており、その意味からも人材育成の基本は「( )が人を育てる」ことにあるといえる。
正解 仕事
問 以下の文章につき、( )に入る語句をそれぞれ答えよ。
クレーム対応では、以下のような点があると解決が難しくなってしまう。
・お客様への( A )理解ができない。
・途中で( B )をしてしまう。
・クレームについての事実の確認ができない。
とくに自分の判断やルールに固執して( C )で反論するとクレームが重大化するケースが多いため、まずはお客さまへの( D )を示した言葉で対応すべきである。
正解 A 心情 B 言い訳 C 正当性 D 共感
テストビジネスでは、クライアントさまのご希望の書籍や資料からの問題作成の他、出題形式、難易度などについても柔軟に対応いたします。
また、試験を受けられる社員さま等の理解度を深め、実務に活かせる研修も行っています。
企業の社内問題の作成についてご質問等がある場合は、お気軽にご相談ください。