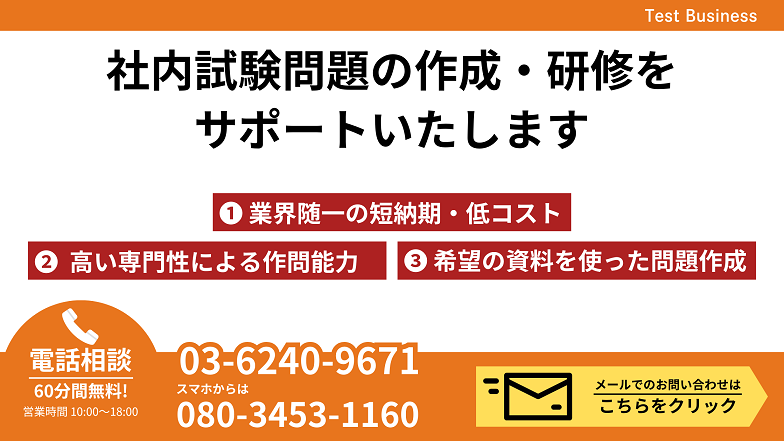社内試験問題見本2
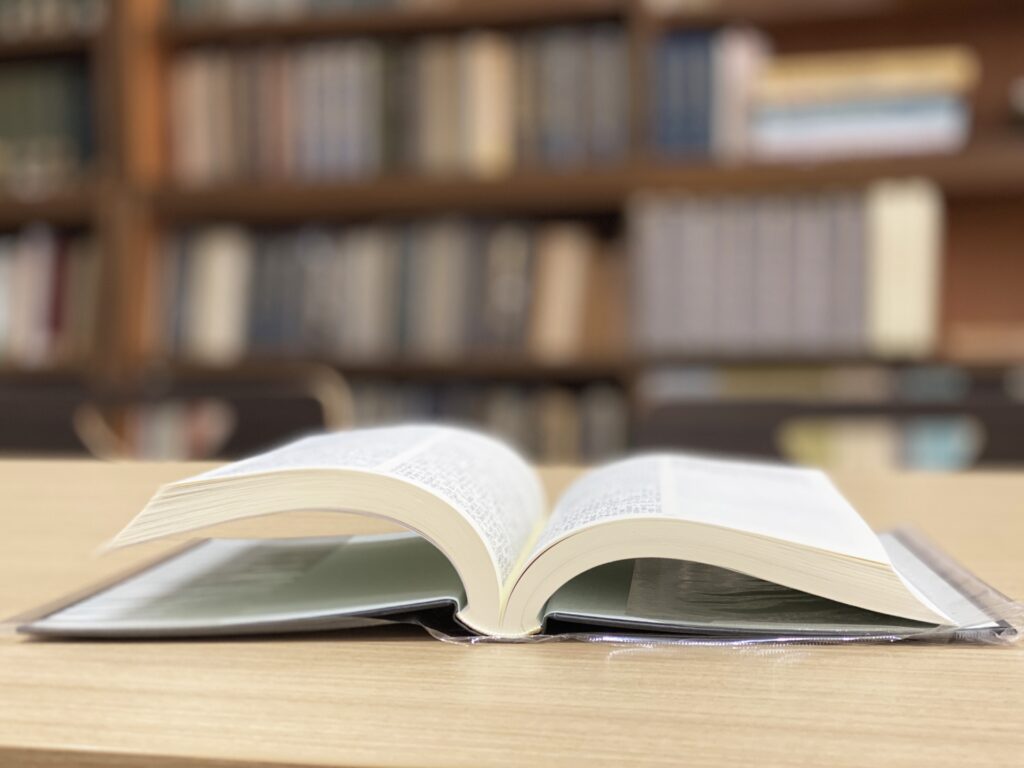
ここでは前回(一般教養、会計、経営分析、マナーその他)に引き続き、マーケティング、法律、コンプライアンス、5S、ドラッガーのマネジメント、内部統制に関する見本問題をご紹介します。
※「社内試験問題その1」についてはこちら
| 社内試験問題見本その1 | 一般教養 経営分析 マナーその他 |
| 社内試験問題見本その2 | マーケティング 法律 コンプライアンス 5S マネジメント(ドラッガー) 内部統制 |
マーケティング
問 マーケティングに関する記述につき、正しいものを選べ。
① マーケティング・コンセプトは、生産指向→顧客志向→販売指向→社会指向という順を追って変遷してきた。
② シーズ、ウォンツ、ディマンズの主体は、いずれも顧客である。
③ 商品本来の価値やサービス価値は、異なった部署でそれぞれを高めることができる。
④ マーケティングミックスにおける価格の要素としては、標準価格、ディスカウント、保証などがある。
正解 ③
問 3C分析とSWOT分析に関する記述につき、正しいものを選べ。
① 3C分析では外部環境として、顧客と会社について分析をする。
② 顧客分析では、自社の直接の顧客を対象とした分析を行う。
③ SWOT分析でマーケティング戦略を考えるときには、客観的な要素だけを使用し、事業方針や経営理念などの主観的な要素は入れない。
④ SWOT分析では、内部環境よりも先に外部環境について分析を行う。
正解 ④
問 商品ライフサイクルに関する記述につき、正しいものを選べ。
① 導入期においては、利益は低いかゼロとなる。
② 成長期では、価格は最も高くなる。
③ 成熟期では、利益は減少に向かう。
④ 衰退期では、商品は差異化される。
正解 ③
問 マーケティングに関する説明につき、誤りを選べ。
① マッカーシーの理論とは、商品を中心としてその周囲にコントロールできる製品、価格、場所、販売促進という4つの要因(4P)が存在するという考え方である。
② 企業の戦略を考える際に特に重要な「4つのC」とは、『自社・協力企業・顧客・競合企業』である。
③ マスコミ×ウェブなどのように、複数のメディアを駆使してより効果的な伝達を狙う広告方法を「クロスメディア広告」という。
④ 製品には「導入→成長→成熟→衰退」のライフサイクルがあるため、そのステージにあわせた戦略や戦術を選択することが重要となる。
正解 ① 商品 → 消費者
問 マーケティング活動を行う際に価格について規制する法律について、( )に入る語句をそれぞれ答えよ。
「マーケティング活動に関する価格を規制する法律のうち、( A )は市場における公正で自由な競争を促進するものであり、一定の価格を維持するための( B )協定や再販売価格維持などを規制する法律である。これに対して景表法は、景品や( C )を規制するもので、( C )の例としては二重価格や希望小売価格の表示などがある。」
正解 ( A ) 独占禁止法 ( B ) 価格 ( C ) 不当表示
問 マーケティングに関する説明につき、正しいものを選べ。
① アウトソーシングとは、経営機能の一部を企業外部から調達することであり、代表的なものとしては、外部の有力な情報関連企業にシステム構築を委託する、情報機器のアウトソーシングがある。
② OEMとは、相手先ブランドによる生産を意味し、参入障壁や移動障壁を乗り越えるのに有効な戦略である。
③ M&Aとは、企業の合併・買収 のことであり 新しい業界や戦略グループに参入するために 最も低いコストで行うことができる方法である。
④ 先発ブランドの優位性は、後発製品よりも大きな利益や市場シェアを獲得できることであり、 これに対して後発 ブランドの優位性は 需要の不確実性の見極めや宣伝広告費の節約ができる点にある。
正解 ③ 最も手っ取り早い方法である
問 「競争地別戦略」に関する説明につき、正しいものを選べ。
① リーダーがとるべき競争戦略は差別化であり、狙うべき市場ターゲットはフルカバーレージとなる。
② チャレンジャーが狙うべき市場目標は市場シェアであり、狙うべき市場ターゲットはセミフルカバーレージである。
③ フォロワーがとるべき競争戦略は集中であり、とるべきマーケティングミックス政策は他社並みかそれ以下の品質、低価格路線などである。
④ ニッチャーが取るべき市場目標は生存利潤であり、とるべきマーケティングミックス政策は高品質、高価格路線などである。
正解 ③
問 3C分析に関する説明につき、誤りを選べ。
① 3C分析における3Cとは、英語の顧客、自社、競合のそれぞれの頭文字をとったものである。
② 3C分析における市場状況とは 具体的には市場規模、成長性、顧客のニーズなどを意味する。
② 3Cの3つの要素において、自社と競合、競合と市場は絶対的な関係にあるが、自社と市場については相対的な関係といえる。
③ 3C分析における自社状況には 理念 ビジョン、事業・製品の現状だけでなく、ヒト・モノ・カネなどの資源も含まれる。
④ 弱者がビジネスで強者に勝つには、特定の市場で競合相手に負けない戦力を投入する必要がある。
⑤ 規模や売上げだけで勝負した場合、戦略や戦術が優れていても、ほぼ勝機はないといえる。
正解 ③ 自社と競合→絶対的関係
問 「満足度の測定効果」の説明につき、誤りを選べ。
① 顧客満足度は、主に既存顧客の維持を目的に行われる伝統的な分析指標であり、顧客の直接調査により測定されるものである。
② 株主満足度は、会社の株主がどれだけ出資に対するリターンに満足しているかを示す指標であり、配当金のほか配当性向や総資産利益率などが指標として利用される。
③ 社員満足度は会社に雇用される社員がその待遇にどれだけ満足しているかを示す指標であり、給与 効果 処遇などの項目を対象として評価される。
④ 社会貢献度とはその会社が社会にどのような役割と責任を果たしているのかを数値化した指標であり、資本金や利益率が高い会社は貢献度が高いといえる。
正解 ④
問 ランチェスター戦略に関する説明につき、誤りを選べ。
① ランチェスター戦略とは、マンチェスター法則やランチェスター戦略方程式をベースに、田岡氏が再構築した日本発の販売戦略&競争戦略である。
② ランチェスターの第2法則によれば、戦闘力は「武器効率×兵力数の2乗」となるため、集団戦では兵力数の差が決定的な勝敗の要素となる。
③ マンチェスターの第二法則は、ビジネスでは戦闘力は販売力に、武器効率は質に、兵力数は量に置き換えられるため、「販売力=質×量の2乗」であるといえる。
④ 会社でのビジネスにおいては、二社間競合の場合は第一法則型を、三社以上の場合には第ニ法則型での戦い方を選択すべきである。
⑤ 遠隔戦・接近戦を流通の視点から考えた場合、接近戦とはエンドユーザーと直接取引をするビジネスが該当し、遠隔戦にはオンライン会議などを活用するビジネスが該当する。
正解 ⑤ オンライン会議→卸や代理店
問 SWOT分析は、内部環境に関する強みと弱み、外部環境に関する機会と「 」の4つの観点から自社の分析をするものである。
①脅威 ②リスク ③競合 ④観察
正解 ①
法律
問 契約は「( )と( )」の意思が合致した時に成立する。
①申込と許諾 ②申込と承諾 ③提供と応諾
問 契約に関する説明につき、正しいものを選べ。
① 有効に契約を締結している場合は、その成立も有効に立証することができる。
② 継続的取引においては 本契約と個別契約の二重の契約を締結するため、契約書中で優先関係を明確にしておく必要がある。
③ 継続的取引の基本契約書には、具体的な金額を記入しないため収入印紙を納付する必要がない。
④ 瑕疵担保責任条項とは、契約の対象物に隠れた価値がある場合に買主が売主に対して負う責任について定めた条項である。
⑤ 契約自由の原則とは 何かに制限されることなく自由に契約を締結することができることをいい、すべての契約について適用される。
正解 ②
問 下請法の規定によれば、親会社には下請け会社に対し( )書面を交付する義務がある。
正解 発注
問 著作権の保護期間は、著作者が生存している期間+( )年間と定められている。
正解 70
問 就業規則とは、職場規律や労働条件を定めたもので、常時( )以上の労働者が働いている職場では必ず作成しなければならない。
①3人 ②5人 ③10人 ④15人
正解 ③
問 休憩・休日に関する以下の文章につき、誤りを選べ。
① 労働時間が5時間30分の場合は、休憩時間を与える必要がない。
② 労働時間が6時間30分の場合は、45分以上の休憩時間を与えなければならない。
③ 労働時間が7時間30分の場合は、1時間以上の休憩時間を与えなければならない。
④ 労働時間が8時間30分の場合は、1時間以上の休憩時間を与えなければならない。
正解 ④ 8時間以下なので、45分以上の休憩時間を与えればよい
問 労働法の背景につき、誤りを選べ。
① 労働三法とは、労働組合法、労働関係調整法、労働基準法のことを指す。
② 労働三権とは、団結権,団体交渉権,団体行動権のことであり、これらの権利を具体化した法律が労働組合法である。
③ 憲法25条の生存権の理念は労働法全体の基本理念であり、そのうちの労働基準法は、憲法27条の労働基本権を具体化するために制定された法律である。
④ 労働法は、規制の見直しや労働者のニーズの多様化を反映し、これまでの集団としての労働者ではなく、個人としての労働者を対象としたものに変わることが求められている。
正解 ③
問 賃金につき、誤りを選べ。
① 会社が任意に支払う給付は原則として、賃金の要件である労働の対象とはならないが、それが就業規則に明記されている場合には、賃金として扱われる。
② 判例によれば、就業規則等において「支給日に在籍している者に限り賞与を支払う」という定めがされている場合でも、その在籍要件の基準が合理的かつ明確である場合には違法とはならないとされている。
③ 判例によれば、退職金を懲戒解雇の場合に不支給とすることや、同業他社への就職の場合に減額することは違法であるとし、賃金が後払い的な性格のものであることを認めた。
④ 成果主義的な賃金制度を採用する会社において、年俸制により支給される給与額がすでに決定されている場合には、その期間中にその額を一方的に引き下げることは認められないとされている。
正解 ③ 功労報酬的な性格のものであることを認め、どちらも原則、違法ではないとしている。
コンプライアンス
問 近時、コンプライアンスが重視されている背景には、「内部通報制度の創設」や「( )の普及」が大きく影響しているといえる。
①口コミ ②SNS ③コミュニケーション
正解 ②
問 コンプライアンス違反を犯した場合、会社においては 配置換え、昇給・昇格の見送り、 減給だけでなく、もっとも重い( )がされることもある。
①けん責 ②諭旨解雇 ③懲戒解雇
正解 ③
問 労働施策総合推進法の改正により、事業主にパワハラを防止する措置を講じることが( )となっている。
①任意 ②義務 ③努力義務
正解 ②
問 製造物責任法による製造物に欠陥があるかどうかは、製造業者がその製造物を( )した時点で判断する。
①契約 ②代金支払い ③引き渡し
正解 ③
問 特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律を( )という。
①チケット不正転売禁止法 ②不正転売防止法 ③古物営業法
正解 ①
問 特定商取引法により指定された契約については、商品購入の契約書面を受け取った日から( )以内であればクーリングオフすることができる。
正解 7日
問 職場における情報を守るための規制は、大きく分けると「守秘義務」、「個人情報の保護」、「( )の保護」の3つとなる。
正解 営業秘密
問 パワハラには、対価型と( )型の2種類がある。
正解 環境
問 取締役の債務について会社が保証するなどの行為は、会社・取締役間の( )として取締役会(取締役会を設置していない会社の場合は株主総会)の承認が必要となり、承認がない場合、その保証は原則として( )となる。
①競合行為・無効 ②越権行為・取消し ③利益相反行為・無効
正解 ③
問 以下の選択肢につき、誤りを選べ。
① 社員が休日の業務外で起こした自動車事故は、会社の指揮命令下で起きたものではないため、会社が使用者責任を問われることはない。
② 「個人情報取扱事業者」に該当しなければ、個人情報保護法の対象とはならない。
③ 顧客Cさんほか多数の個人情報データを処理するため、Cさんからの同意を得ずに、委託先のデータ処理会社であるY社に個人情報のデータを渡した。
④ 法令違反ではなく、社会ルールに違反する行為もコンプライアンス違反となる。
正解 ①
5S
問 5Sとは、整理・整頓・清掃・「 」・躾の5つの目的を持った活動のことをいう。
①仕組み ②整然 ③清潔 ④掃除
正解 ③
問 本物の5S活動を通じてこそ、全員参加で社員が知恵を出し、職場のムダを取り、利益を生み出す職場体質を作ることができるのであって、そのための唯一の方法が本物の5Sの定着と職場の( )である。
正解 見える化
問 あ・じ・か・げん運動の「じ」とは、( )の頭文字である。
正解 三現主義
問 オフィスの整理は、情報の整理を中心に進める。情報整理は( )によって、必要な情報がすぐに見つけられるようにする。
正解 ファイリング
問 「5S立看板」や「5S( )図」などによる見える化をすることで、形だけの5S活動となることを防ぐことができる。
正解 定義
問 定置は必要に応じて変化させ、生産現場を( )に維持しなければならない。
正解 ジャストインタイム
問 5Sとは、整理・整頓・清掃・( )・躾の5つの目的を持った活動のことで、その目的は「人づくり」をして、「カイゼン」職場をつくることである。
正解 清潔
問 ( )とは、人が持っている視覚のパワーを活用して、新人の作業者でも「今日、何をどうやったらよいのか」がわかる 職場環境を作ることである。
正解 見える化
問 整頓における「定置」の3要素は、「置き場所」、「置き方」、「( )」である。
正解 表示方法
マネジメント(ドラッガー)
問 「われわれの事業は何か」を問うことこそ、組織の責任である。
正解 ✕ 組織→トップマネジメント
問 コミュニケーションと情報は相反するが、両者は依存関係にある。
正解 〇
問 チーム型組織の特徴として、明快さと安定性に優れる、硬直的であって適応性に欠けるなどがある。
正解 ✕ 文章は、職能別組織の特徴である。
問 ( )とは、人的資源や物的資源に対し、より大きな富を生み出す新しい能力をもたらすことである。
正解 イノベーション
問 労働には、生理的、心理的、社会的、( )、政治的という5つの次元がある。
①本能的 ②経済的 ③義務的
正解 ②
問 イノベーションに関する説明につき、誤りを選べ。
① イノベーションの結果、もたらされるものが値下げだとしても、それは価格だけが定量的に処理できるものだからそう見えるのであり、イノベーションがもたらすものの本質は、よりよい製品や便利さ、より大きな欲求の満足そのものである。
② イノベーションは発明や技術といった部分的な職能ではなく、企業のあらゆる部門や活動に及ぶものであり、人的資源や物的資源に対し、より大きな富を生み出す新しい能力をもたらすものである。
③ イノベーションは、新規の製品や発明のみから生み出されるものではなく、既存の製品を利用したものでも、その中から新しい用途を見つけ、市場を開拓することは、イノベーションといえる。
④ イノベーションは、顧客を創造するという企業の目的のための機能の一つであることから、これによるマネジメントは社会的なニーズではなく、個人ごとの顧客を中心としたニーズを事業機会として捉える必要がある
正解 ④
問 「人と労働のマネジメント」に関する説明につき、誤りを選べ。
① マグレガーのX理論は、人は怠惰で仕事を嫌い、強制しなければ自ら責任を負うことのできない未熟な存在と位置づけたのに対し、Y理論は、人は欲求を持ち、仕事を通じて自己実現と責任を欲するという、人を成人として認める立場のものである。
② 現在の産業心理学の中身は、心理操作による支配であり、その実態はX理論と変わるものではなく、また、その適用には支配する側に万能なマネジメントが必要となるため、取り入れるのが難しい側面がある。
③ 働くことに関わるマネジメントの成功例では、権限の組織化に焦点を当てることが重要なポイントであり、その代表例が家族的マネジメントや参加型マネジメントなどである。
④ アメとムチに依存することなく、働くことによる成果と自己実現を成功させた例の1つとして、ツァイスのアッベが、現場で働く者たち自身に職務を設計させ、責任を負わせる方法で、働くことと働く人のマネジメントを行ったことがあげられる。
正解 ③ ※働くことに関わるマネジメントの成功には、権限の組織化ではなく、責任の組織化が重要となる。
問 「人は最大の資産である」に関する説明につき、誤りを選べ。
① 本来、マネジメントは権力を持たず、責任を持つだけであり、その責任を果たすために権限を必要とするだけである。しかし、多くの企業が、マネジメントは権限の放棄を要求するものという、権限と権力を混同した誤解によって働く者に主体的に成果を上げさせるという課題を直視していない。
② 人が雇われるのは、その強みの上であり、能力の上であることから、人のマネジメントによる組織の最大の目的は、人の強みを生産に結びつけ、人の弱みをなくすことにある。
③ かつて分権化のシステムは、トップマネジメントを弱体化し、失権を招くと心配されて反対を受けたが、日本企業やIBMが成功した理由は、分権化がマネジメントの権限を強くすることを知っていたことによるものである。
④ 働く者に主体的に成果をあげさせるという課題の解決のために必要なのは、仕事と職場に成果と責任を組み込み、働く人たちを生かすべきものと捉える中で、適材適所に人を配置することである。
正解 ② ※人の弱みをなくすことはできないため、これを中和する組織の目的とするべきである。
問 「マネジャーの仕事」に関する説明ににつき、誤りを選べ。
① 専門家は、成果を上げるために自らのアウトプットを他者のインプットにする必要があり、その際に重要となるのがコミュニケーションであるが、このことを専門家に認識させ、サポートするのがマネジャーの仕事である。p148(専門家の課題)
② 以前のマネジャーに関する定義では、管理するものはより多くの報酬を受けるとの意味あいがあったが、現在の専門家についてこの定義は意味をなさず、現在、マネジャーと専門家を区別する違いは、マネジャーがその職務を果たすための機能や貢献の差にあるといえる
③ マネジャーにとって最も重要であり、学ぶことのできない、先天的な資質は才能ではなく仕事に対する真摯さであるが、その成果を 十分に発揮させるためには、十分な大きさと重さの仕事を割り振る必要がある。
④ マネジャーの仕事は、本来の仕事、割り当てるという仕事、上下横との連携、情報の管理と活用という4つの視点から設計されなければならないが、これらについて自らが期待されることを理解し、考えることがマネジャーにとっての最大の責任である。
正解 ① ※マネジャーと専門家を区別する違いは、その責任と活動においてマネジャーが仕事に対する手段を持つという点にある。
内部統制
問 「内部統制のメリット・デメリットや仕組み」に関する説明につき、誤りを選べ。
① 内部統制には、「コストが増えたり、現場のスピードが落ちる」という 側面もあるが、それは内部統制を構築しない場合にかかるコストやリスクを考えていない、現状の業務に対する悪影響のみを見た意見である
② 内部統制の構築では、コストとリスクのバランスを考慮する必要があるが、バランスよく 構築された内部統制は、企業にとって不可欠な「業務の有効性・効率性」、「 コンプライアンス」、「適切な財務報告」、「 資産の保全」という4つの目的に貢献する。
③につき、誤りを選べ。適切な内部統制が構築されていることは、企業イメージの向上やブランド価値の向上だけでなく、不祥事による損害を避け安定した経営ができるという企業にとって、直接的な利益をもたらすものである。
④ 内部統制の仕組みは、現金や支払いの管理から始まったものであるが、現在のような情報システムの高度化やグローバル化が進む中では、内部統制を組み込む必要性がさらに高まっている。
正解 ③ ※ 内部統制は、直接的な利益を会社にもたらすものではない。
問 内部統制の基本的要素である統制環境につき、誤りを選べ。
① 内部統制の基本はすべての企業に共通するものであるため、目指すべき内部統制の組織体制は企業の規模や方針により左右されることはない。
② 統制環境は、他の基本的要素の基礎をなし、影響を及ぼす基盤であるため、統制環境の機能が十分でない場合には、他の要素も適切に機能することはない。
③ 経営者は、内部統制を実行するにあたっては、過度な利益追求を戒めるだけでなく、 機能を十分に発揮するための経営資源の配分にも注意する必要がある。
④ 企業が内部統制の目的を達成するためには、必要な役割を各部署や個人に分担させる必要があるが、その際にはそれに伴い必要な権限と責任を与えることがセットで必要となる。
正解 ① ※内部統制を有効に機能させうる組織体制は、企業の方針や規模により大きく異なる。
問 内部統制の限界につき、誤りを選べ。
① 当初、想定されていなかった新しい技術の変化が起きた場合や、それまで行われてこなかった取引を新たに行うような場合には、従来の内部統制では対応できない可能性がある。
② 内部統制の整備・運用に際しては、コストとベネフィットを考えた場合、内部統制を構築しないという判断も必要となる。
③ コストを考慮した場合、リスクの高い分野から重点的に内部統制の構築をしなければならない以上、すべてのものに対して内部統制をすることはできないことを理解しておくべきである。
④ 経営者に内部統制を無視した行動をする意思がある場合でも、適切な内部統制のシステムが機能していれば、未然にこれを防ぐことが可能となる。
正解 ④ ※経営者に内部統制を無視した行動をする意思がある場合、業務プロセスによる内部統制でこれを防ぐことは難しいため、このような場合は内部統制の効果は限定的となる。
問 内部統制と法令の関係につき、誤りを選べ。
① 会社法と金融商品取引法では、それぞれにおいて内部統制の構築や評価方法に関する基準が定められているため、実際の運用においては、該当するものを適用するように注意する必要がある。
② 会社法では、内部統制という用語は使用されていないが「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適性を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制」がこれに当たるとされる。
③ 金融商品取引法では、上場企業が企業グループの財務報告にかかる内部統制について評価を行い、その報告書を有価証券報告書とあわせて提出することが義務付けられており、これがいわゆるJ- SOXとして知られている制度のことである。
④ 金融商品取引法においては、内部統制の4つの目的のうち、「財務報告の信頼性」のみが対象となっているのに対し、会社法ではすべての目的が対象とされている。
正解 ① ※金融商品取引法では具体的な基準が定められているが、会社法では示されていないため、金融商品取引法の基準を会社法基準として利用することができる。
テストビジネスでは、クライアントさまのご希望の書籍や資料からの問題作成の他、出題形式、難易度などについても柔軟に対応いたします。
また、試験を受けられる社員さま等の理解度を深め、実務に活かせる研修も行っています。
企業の社内問題の作成についてご質問等がある場合は、お気軽にご相談ください。