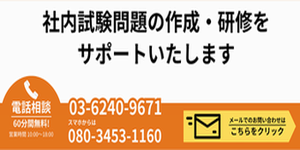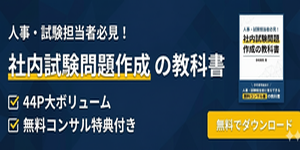営業担当者が知っておくべき。取引先の確認ポイントと代金回収に効果的な研修を紹介!
企業が存続していくためには、売上げを上げることが不可欠ですが、それと同じぐらいに重要なのが「代金の回収」です。
どんなに売り上げを上げても1回の回収不能が生じれば、その何倍もの利益が吹き飛んでしまいます。
そのため、危ない取引先を見分ける能力や、いざというときの代金回収のスキルは必須であり、これらのノウハウを研修に取り込むことでリスクを大きく減らすことができます。
この記事では、危ない取引先を見分けるためのポイントや、代金を回収の手続き、そのための研修内容について解説いたします。
代金が回収できない場合のリスク
現在、ほとんどの企業で、信用取引(「売掛・買掛」)による決済が行われています。
しかし、これらの取引には担保や引当がないため、代金が回収できないと次のようなリスクを生じます。
利益がなくなる
1回の取引でどの程度の売上げと利益が出るかは、業種や原価率等により異なります。
しかし一般的には、売上高経常利益率は小売業で3.1%、卸売業で3.4%とされています。
そのため、仮に代金の回収できない場合、残りの97%分を新たな売り上げで取り戻すには、30倍以上を売り上げなくてはならなくなります。
また、会社が借入れをしている場合には、その元本の返済は税引き後利益から行いますが、代金の回収ができなければ、この返済原資も失われることとなります。
資金繰りが悪化する
信用取引を行っている会社では、契約で定められた回収条件に従い、将来入ってくる資金の使い道を予測する必要があります。
この作業を「資金繰り」といいます。
資金の使い道には、原価や人件費、買掛金の支払いなどがありますが、代金の未収が発生すると、予定通りの仕入れや支払いができなくなる可能性があります。
また、手元の資金で対応ができない場合には、新規に借入れをしなければならなくなるため、財務的な負担が大きくなります。
信用が悪化する
代金の未収が多い会社は、「資金管理ができていない会社」、「調査力がない会社」などと評判になり、信用を失うこととなります。
また、代金の未収が繰り返されると、それにつけ込む詐欺や犯罪に狙われやすく、リスクの高い取引が増えやすくなります。
代金の未収を出さないためのチェックポイント
代金の未収を出さないためには、未収が発生したときだけでなく、契約をする前からしっかりと調査し、対策することが重要となります。
取引先の会社の登記事項証明を確認する
取引先が法人の場合は、法務局にその会社の登記事項証明書(以前の登記簿謄本)が用意されているので、取引を始める前には必ずこれを取得して内容を確認しておきます。
登記事項証明書で確認すべき主な項目は、以下の通りです。
| ● 法人登記がされているか? ● 本店や代表者の住所は本当に存在するか? ● 頻繁な移転や大幅な目的変更をしていないか? ● 役員に問題のありそうな人間はいないか? ● 資本金はどの程度か? |
法人登記がされているか?
もし、法人や◯◯会社と名乗っているにも関わらず、登記事項証明書が取得できないときは、そもそも会社が存在していないので、その時点で即刻取引を中止すべきです。
なお、相手が個人事業主の場合には登記事項証明書はありませんが、その場合には税務署へ提出した開業届のコピーで実体があるのかどうかを確認します。
本店や代表者の住所は本当に存在するか?
登記事項証明書で会社の本店(住所にあたるもの)がわかったら、まずはそのような住所が存在するのか(架空の住所でないか?)を確認します。
そして、住所の存在が確認できたら、住宅地図やGoogleのストリートビューなどで次の点を調査します。
▼ その場所に該当する建物があるか?
▼ 地図上の名前と会社の商号が一致するか?
該当する場所に建物がない、空き地や駐車場になっている、民家であるなどの場合には、その住所は架空だと考えられます。
また、看板はあるが、地図と登記上の商号が異なる場合には、「現地に行って確認する」、「遠方の場合には、第三者に確認を依頼する」などの方法でさらに詳細な調査を行います。
もし、可能であれば、茶園会社の公共料金の控えなどを見せてもらうのもよいでしょう。
登記事項証明書の役員欄には、
▼ 株式会社の場合 - 代表取締役の氏名・住所
▼ 合同会社の場合 -代表社員の氏名・住所
が必ず記載されているので、この住所についても本店の場合と同様に、調査をします。
頻繁な本店の移転や大幅な目的変更をしていないか?
短期間で、頻繁な本店の移転や大幅な目的変更をしている場合は、注意が必要です。
なぜなら、このような会社は休眠会社や倒産寸前の会社を買い取り、商号や本店、目的を変更したうえで、詐欺の舞台に利用していることが多いからです。
このような会社は、登記事項証明書に
▼ 「〇年〇月〇日商号変更」
▼ 「〇年〇月〇日目的変更」
▼ 「◯年◯月◯日に◯◯県◯◯市◯◯から本店移転」
と記載されているのが一般的です。
これらはいずれも、以前の会社の経歴を消すために行われますすが、その場合でも、閉鎖謄本を取得すれば過去の会社の履歴を確認することができます。
役員に問題のありそうな人間はいないか?
役員が複数いる場合は、それぞれを検索して、
●「過去に事件や問題を起こしていないか?」
● 「暴力団との関係がないか?」
●「よくない噂や評判がないか?」
などを確認します。
なお、代表者については設立登記をする際に印鑑証明書の提出が義務付けられています。
しかし、それ以外の役員については裏付けがなくとも登記ができるため、本当に実在するのかについても注意が必要です。
資本金はどの程度か?
最近では資本金が1円からでも登記ができるため、資本金の額は以前ほど問題ではなくなっています。
しかし、資本金があまりに少ない場合には、ちょっとした資金ずれや売上げの見込み違いなどで、倒産してしまう可能性が高いといえます。
そのため、取引額に見合う程度の資本金があるのかも、リスクを避けるポイントとなります。
その他の項目で確認する
登記事項証明書以外でも、次のような確認することができます。
インターネットで情報を取得する
最近では、ほとんどの会社でホームページを持っているのが当たり前となっています。
なので、ホームページのアドレスがわかる場合には、そのページを閲覧し、ホームページに記載されている会社の概要と登記事項証明書の内容(とくに本店所在地や役員)に相違がないかを確認します。
また、インターネットで「会社の名前+評判」などのキーワードで検索することでも、有力な情報を見つけられることもあります。
監督官庁で確認する
対象の会社等が何らかの国家資格(建設業や不動産業、〇〇士など)により営業している場合には、その監督官庁のホームページの名簿を見ることで、本当にその資格の登録がされているかどうかを確認することができます。
また、国家資格でない場合には、「本当にそのような資格があるのか?」、「実際に機能している資格なのか?」などについて調査します。
会社の番号につながるのか?
名刺などにより会社の番号がわかる場合には、実際にその番号に電話をし、本当にその番号が存在するかを確認します。
「いつもでない」、「通話ができない」などの場合は論外ですが、常に「秘書サービスに転送される」などの場合も要注意といえます。
代表者の身分証明書をコピーする
詐欺やその他の犯罪を計画している場合には、会社の情報を見せることはあっても、代表者が自分の個人の情報を見せることはなく、多くは偽名だったりします。
そのため、取引をする前には、名詞だけでなく、シッカリと代表者の免許証等のコピーを取って身元を確認しておく必要があります。
金融機関の口座情報を確認しておく
仮に、会社や代表者の素性に問題がない場合でも、新設の会社などはすぐに支払い不能や経営破綻してしまうこともあります。
そのため、万が一の場合に備えて重要なのが、「相手の金融機関の口座情報」を確認しておくことです。
なぜかといえば、相手が訴訟で敗訴しても任意に支払いをしない場合には、相手の預金口座を差し押さえるため金融機関名や口座番号などがわかっている必要があるからです。
これらの情報は、トラブルになってからでは入手することは難しく、また、金融機関でも公開しないため、関係が良好なうちに手にいれておく必要があります。
なお、取引先の金融機関の情報は、会社の決算書の「取引先金融機関」の欄に記載されているで、できれば決算書を入手することをお勧めします。
しばらくの間は半額以上を先に現金でもらう
取引を開始する場合は初回だけでなく、その後しばらくの間は現金でもらうようにします。
通常、2~3回程度までは現金でもらい、その後は売掛取引とするケースが多いと思います。
しかし、取込詐欺などでは、掛取引になったタイミングで詐欺を仕掛けてくることが多いため、「大丈夫」という確証が持てるまでは、半額以上の掛売はしない方がよいでしょう。
決算書を提出してもらう
詐欺をもくろむ会社では、名刺や豪華な応接室、有名人との写真、架空の取引実績などにより信用力があるように見せかけます。
しかし、決算書までは用意していないのが普通であり、これを作成していたとしても、たいていは実質的な取引がないことがその内容からわかります。
なお、決算書は、貸借対照表と損益計算書だけでなく、 必ず勘定科目明細やその他の部分を含めた一式すべてを提出してもらうようにします。
とくに、勘定科目明細には、使用している銀行口座や取引先、借入先などの情報が含まれているため、重要な資料となります。
もし、内容の読み取りに自信がない場合は、顧問税理士などの専門家に確認をお願いしましょう。
相殺の準備をしておく
相殺とは、自分と相手に同じ種類の債権(例えば、商品の売買代金)がある場合に、債権同士を対等額で打ち消し合うことで、清算する法律行為のことをいいます。
相殺は条件が整えば、相手の同意なしで、一方的な意思表示だけでこれを行うことができるため、代金の回収に役立てることができます。
例えば、取引先であるA社が代金の支払いに応じてくれない場合、A社が販売している商品を購入して、双方の支払いを相殺するなどが考えられます。(購入したものは売却)
ただし、有効に相殺をするには、一定の条件が必要となるため、あらかじめ専門家に相談することをおすすめします。
代金未払いの場合の手続き
取引先の会社に代金を支払ってもらえない場合は、次のような方法で回収を図ります。
メールや文書による督促
代金の支払いが期日までにされないときには、まずはメールまたは手紙などで支払いの督促を行いますが、メールと文書ではそれぞれに一長一短があります。
【メールによる場合】
メールによる督促は、簡単かつリアルタイムで行うことができるため、まずは最初に取るべき手段となります。
また、メールの場合は、発信時の記録を残すことができる点でも優れています。
しかし、手軽にできる分「相手に軽んじて扱われる」、「相手が見ていない場合がある」などのリスクがあります。
【文書による場合】
文書による督促は、あらたまった感じを演出することができるため、メールによる場合よりも、相手により強いプレッシャーを与えることができます。
しかし、これにより相手の態度が硬化してしまうこともあるため、メールでの督促で効果がない場合に行うべきといえます。
内容証明の送付
メールや手紙による督促をしたにも関わらず、返信がない、無視されるなどの場合には、内容証明による督促をします。
内容証明は、督促をした事実を公的な記録として残すとともに、一時的に時効を中断させるといった法的な効果があります。
しかし、これ自体で支払いを強制するものではないので、あくまでも督促をしたという事実を残すものと考えた方がよいでしょう。
内容証明は裁判時において重要な証拠資料となります。
けれど、書かれた内容は相手にとっても証拠となり得るため、内容によってはこちらにとって悪材料となる可能性があることに注意する必要があります。
支払い督促手続き
内容証明郵便で支払いを請求しても相手が応じない場合には、裁判によらなくとも比較的簡単な手続きで支払いを督促できる仕組みがあります。
この手続きを「支払督促」といいます。
「支払督促」とは、代金の支払いがされない場合に、簡易裁判所の書記官が相手方に金銭の支払いを命じる制度です。
書類審査のみで迅速に解決を図れ、費用も訴訟の場合の半分となっていることから、少ない負担で行うことができます。
支払督促は、申立人の申立てにもとづいて、裁判所書記官がその内容を審査し、相手方の言い分を聞かないで金銭の支払いを命じるため、迅速に処理することができます。
もし、支払督促に対して相手が異議申立てをしない場合には、仮執行宣言を付けてもらうことができるため、その場合にはこれにもとづいて強制執行をすることが可能となります。
ただし、相手が支払督促に異議の申立てをした場合には、支払い督促は効力を失い、そのまま訴訟に移行してしまうことに注意する必要があります。
訴訟(少額訴訟を含む)
通常の訴訟
民事訴訟は、訴額(紛争の対象となる金額)が140万円以下の場合は簡易裁判所で、140万円を超える場合は地方裁判所で行われます。
通常訴訟では、裁判官が認めれば証書(文書による証拠)に限らず、証人や当事者への尋問、鑑定などすべての証拠について取り調べをすることができます。
ただし、その分時間がかかることが多く、審理が行われる頻度も1ヶ月に1回程度のため、最終的な判決が出るまでには数か月から年単位での時間がかかります。
また、自分で訴訟をすることができない場合は、弁護士に依頼する必要があります。
少額訴訟
少額訴訟とは、60万円以下の金銭の支払を求める場合に限り、利用できる簡易な訴訟です。
原則として、1回の審理で判決を得ることができるため、短期間・少額の費用で行うことができます。
また、訴訟の途中で話合いにより解決(和解)することもできます。
ただし、提出できる証拠は、その場で内容を確認できる書類に限られ、証人尋問や鑑定の手続きなどは行うことができません。
なお、少額訴訟で和解をした場合も、判決と同様に強制執行することができます。
訴訟等にかかる費用
訴訟や支払督促をする場合には、以下の手数料が必要となります。
法定手数料(裁判等をするための費用)
| 訴 額 | 訴訟の場合 | 支払督促の場合 |
| 10万円 | 1,000円 | 500円 |
| 50万円 | 5,000円 | 2,500円 |
| 100万円 | 10,000円 | 5,00円 |
| 200万円 | 15.000円 | 7,500円 |
その他の費用
訴訟等の費用は,基本的には敗訴者の負担となります。
そのため、自分が敗訴した場合には、相手の法定手数料のほか,書類を送るための郵便料及び証人の旅費日当等を負担しなければなりません。
ただし、弁護士費用はこれに含まれないのが原則です。
したがって、弁護士費用ついては、裁判の勝敗にかかわらず、自分で負担する必要があります。
| <参考>弁護士費用の相場 ・着手金:定額または訴額の約5~10% ・報酬金:回収金額の約10~20% |
なお、勝訴判決を得ても相手が支払いをしない場合には、差し押さえをする必要がありますが、強制執行手続きについては別途に費用が必要となります。
代金回収スキルのための研修
以上のように、代金の回収には主に法律に関する知識が必要となるため、効果的に回収手続きを行うには、次のような研修をすることをお勧めします。
代金回収のための法律知識
民法
民法はあらゆる私人間の法律関係を規定する法律であるため、この知識は必須となります。
とくに、代金の回収については、民法債権編の売買・相殺・連帯保証・契約(成立・効力・解除)。消費貸借などの項目が重要となります。
民事訴訟法
民事訴訟法は、裁判をする場合の手続きを定めたもので、実際に裁判を検討するときに必要な知識となります。
通常、裁判手続きは弁護士が行いますが、その場合でもどのような流れで裁判がされるのかや、費用がどのくらいかかるのかなどの検討には、民事訴訟法の基礎的な知識が必要となります。
また、少額訴訟や支払督促は自分だけでもできるため、研修でその申立書の書き方などをレクチャーしておくと、実務でも役立ちます。
契約書の作成
法律的に問題がなく、かつ効果的な回収をするには、契約書で未払いが生じたときの取り扱いや違約条項を定めておくことが重要となります。
契約作成時に必要となるものとしては、以下のような項目があげられます。
| ● 契約成立の条件 ● 支払いの期限 ● 責任の負担の取り扱い ● 契約の解除の方法 ● 遅延利息や違約金の定め ● 合意管轄 |
なお、合意管轄とは、裁判を提起する場合に自分と相手の会社のどちらの地域の裁判所で裁判するのかを定めるものです。
相手との距離が離れている場合にはとくに重要な項目となります。
督促文書等の作成
代金の回収の成否は、はじめに行う督促の仕方や内容によって大きく影響されます。
したがって、督促をする場合には、感情的ではなく、法的に問題のないポイントを押さえた文書を作成することが重要となります。
代金の督促文の例としては、以下のようなものがあります。
【督促文の例】
株式会社〇〇〇〇 〇〇部〇〇課 〇〇 様 令和〇年〇月〇日
▲▲株式会社 総務部〇〇課〇〇
入金未納のご確認について
平素より大変お世話になっております。株式会社◯◯、総務部の◯◯です。
さて、先般、貴社にてご購入いただきました「〇〇」の料金(〇〇円)についてですが、お約束の期日(令和◯年◯月◯日)を過ぎてもご入金が確認できておりません。
つきましては、お手数をおかけいたしますが、再度、内容のご確認をいただき、お手続きがお済みでない場合は〇月〇日(〇曜日)15時までに指定の口座までご入金いただきますようお願い申し上げます。
■ご請求の詳細
未入金代金:〇月ご請求分(商品名:◯◯購入代金分)
金額:〇〇,〇〇〇円
お振込先:〇〇銀行 〇〇支店 普通 口座番号〇〇〇〇〇〇〇
なお、ご入金をいただいた際には、本メールアドレスにその旨のご連絡をいただきますようお願いいたします。
もし、本メールと行き違いでお振込みいただいている場合は、何卒ご容赦ください。
※ご都合によりご入金が遅れる場合は、予めご入金日をご連絡いただきますようお願いいたします。
お忙しいところ大変恐縮ですが、ご対応の程、何卒宜しくお願い申し上げます。
なお、効果的な研修を行うには、内容に合った目的の設定や段階的なアクションが重要となります。
以下の記事ではこれらについて解説していますので、あわせて御読みください。
まとめ
代金等の未収を生じさせないためには、事前に相手の信用調査や与信管理を行っておくことが重要です。
また、営業や経理、法務などに携わる方は、法的な対応が必要な場合に備えて、研修などで手続きに関する知識や文書作成スキルを習得しておくことをお勧めします。
| テストビジネスでは、社内試験問題の作成・実施に関するご相談を承っております。 また、ご希望の方には、正式なご依頼前に無料で見本問題を作成・ご提出するサービスもございますので、お気軽にお問合せください。 |